「健康診断で動脈硬化のリスクがあるといわれた」
「動脈硬化は何が原因で起こってしまうの?」
健康診断などで動脈硬化の疑いがあると指摘されて、気になっている方もいるかもしれません。
動脈硬化が進行してしまうと、重大な脳心血管疾患につながるリスクもあります。動脈硬化を改善するには、まずは原因を知った上で、生活習慣を改善することが大切です。
本記事では動脈硬化の種類や原因、動脈硬化を予防するために改善すべき生活習慣のポイントをご紹介します。
1.動脈硬化とは
動脈硬化とは、血液を全身に運ぶ動脈の血管が硬くなり、弾力性を失ってしまった状態です。
本来は弾力性があるはずの動脈がさまざまな原因によって硬くなってしまうと、心臓や全身の臓器が正しく機能しなくなります。
動脈は内膜・中膜・外膜で構成されており、動脈硬化の起こる部位や起こり方によって3三つのタイプに分けられます。
1-1.アテローム動脈硬化(粥状動脈硬化)
アテローム動脈硬化とは、動脈の内膜に悪玉コレステロールなどのドロドロになった脂肪のかたまりができるタイプの動脈硬化です。かたまりとなった脂肪は「プラーク」と呼ばれます。
プラークが太い血管に詰まってしまうことで、重大な心疾患や脳血管疾患につながるため、最も注意が必要です。
1-2.細動脈硬化
細動脈硬化とは、脳や腎臓、目などの細い動脈の内膜・中膜・外膜の3層とも硬化した状態です。
高血圧や加齢が原因になることが多く、通常、血栓やプラークの形成はありません。硬化が進行していくと動脈が破裂し出血に至る恐れがあります。
1-3.メンケベルグ型硬化(中膜硬化)
メンケベルグ型硬化とは、動脈の中膜にカルシウムが蓄積され石灰化して硬化した状態です。
大動脈や足、首の動脈に発生しやすく、硬化が進行すると中膜がもろくなり、破れてしまうこともあります。
2.動脈硬化の原因
動脈硬化は「血管の老化」とも言われますが、その原因は単なる老化のみではありません。さまざまな疾患や生活習慣が重なり合って動脈硬化が進行していきます。
ここでは動脈硬化の原因となる疾患や生活習慣について解説します。
2-1.高血圧
高血圧とは、生活習慣や全身の臓器の不調により引き起こされ、症状が現れることが少ないことが特徴です。
高血圧になると血管に過剰な負荷がかかってしまい、動脈硬化が進行してしまいます。
さらに、動脈硬化が進行すると血管が弾力性を失ってしまい、高血圧も進行してしまうという悪循環に陥ってしまいます。
2-2.糖尿病
糖尿病とは、インスリンが上手く働かなかったり、分泌されなかったりすることで血液中のブドウ糖が過剰になってしまう病気です。
糖尿病の原因として挙げられる肥満は、それ自体が動脈硬化にもつながる恐れがあります。さらに、酸化ストレスによって血液中に過剰となったブドウ糖は血管壁を傷つけて動脈硬化を進行させてしまいます。
2-3.脂質異常症
脂質異常症とは、血液中の脂質の値が基準値から外れた状態のことです。一般的に、悪玉コレステロールまたは中性脂肪が過剰にある、もしくは善玉コレステロールが異常に少な過ぎる状態を指します。
血液中の悪玉コレステロールが増加すると、動脈の内部にコレステロールが蓄積され、次第に血管壁が硬く分厚くなり、アテローム動脈硬化を招いてしまいます。
一方、善玉コレステロールは、正常であれば動脈硬化の進行を妨げるはたらきを持ちます。しかし、減少すると上手く機能しなくなり、結果的に余分なコレステロールが血管壁に溜まってしまうのです。
2-4.肥満
肥満も動脈硬化を引き起こす原因となります。
なかでも内臓周辺に集中して脂肪がつくタイプの内臓脂肪型肥満の方は要注意です。内臓脂肪型肥満になってしまうと、脂質異常症や糖尿病、高血圧といった生活習慣病になりやすくなります。
肥満に加えて生活習慣病も引き起こされ、その数が多いほど動脈硬化の進行リスクも上がってしまうのです。
2-5.喫煙
たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、動脈の炎症や収縮を引き起こす作用があります。
主に悪玉コレステロールを増やしたり、善玉コレステロールを減らしたりする作用があるため、動脈硬化を進行させるのみならず、心疾患や脳血管疾患にかかる恐れがあります。
また、喫煙本数の増加により、動脈硬化が原因で冠動脈疾患の死亡リスクが高まるともいわれています[1]。
2-6.ストレス
動脈硬化が原因として発症する病気に心筋梗塞が挙げられますが、その発症の要因については、ストレスに関わりがあるといわれています[2]。
ストレスを受けると交感神経が優位になり、血圧が上昇します。これにより、動脈硬化の進行をもたらし、結果的に心筋梗塞を引き起こす可能性があるのです。
3.動脈硬化が進行するリスク
動脈は全身に流れているため、動脈硬化による影響は心臓や脳、手足といった至るところに現れます。
ここでは特に注意が必要な疾患について解説します。
3-1.狭心症
狭心症とは、心臓を取り巻くように走行している冠動脈が細くなって血液が流れにくくなる疾患です。動脈硬化のなかでも、アテローム動脈硬化が進行することによって狭心症が起こりやすくなります。
症状としては、歩行や運動などをした際に胸の痛みや圧迫感が現れるものの、数分以内で治まるのが特徴です。
3-2.心筋梗塞
心筋梗塞とは、アテローム動脈硬化によって形成されたプラークが剥がれて血栓となり、冠動脈に詰まってしまう疾患です。
狭心症と違い、心臓への血流が完全に途絶えてしまうため、血流が失われた血管の支配する部位や範囲によっては、発症後すぐに処置をしないと突然死に至ることもあります。
3-3.脳梗塞
脳梗塞とは、脳に走行する動脈が梗塞してしまい、脳細胞への血流が途絶えてしまう疾患です。脳梗塞が起こった部位によって症状が異なり、片方の手足の麻痺、言葉が出にくい、めまい、視野が欠ける、意識障害などが代表的です。
脳梗塞が起こる原因によって「ラクナ梗塞」「アテローム血栓性脳梗塞」「心原性脳梗塞」に分けられます。
なかでもアテローム血栓性脳梗塞は動脈硬化と深い関係があります。
3-4.脳出血
脳出血とは、脳の細かい血管が破れて出血を起こし、脳細胞が破壊される疾患です。
脳出血の症状は部位や出血量により異なりますが、めまいや吐き気、頭痛、意識障害、手足の麻痺、言葉が出にくくなるなどが挙げられます。
動脈硬化により血管が硬くもろくなっていると破れて出血しやすい状態であり、加えて血圧も高くなりがちなので血管へのダメージが大きくなります。
3-5.末梢動脈疾患
抹消動脈疾患とは、動脈硬化により足の血管が細くなったり、詰まったりすることで血流が途絶える疾患です。
足への血流が途絶えることで歩行時の痛みやしびれ、冷感といった症状が起こります。さらに症状が悪化すると歩けなくなり、足が壊死してしまう恐れがあります。
4.動脈硬化を予防するために大切な7つのこと
動脈硬化は生活習慣のさまざまな危険因子が複雑に絡んで発症、進行していきます。そのため、生活習慣を改善し、一つでも多く危険因子を減らすことが大切です。
ここでは生活習慣を改善し、動脈硬化を予防するために大切な七つのことを解説します。
4-1.1日の総エネルギー摂取量を適正にする
肥満は血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を増加させるため、1日の総エネルギー摂取量を適正に保つことが大切です。
適正な総エネルギー摂取量は以下の式で求められます。
例えば、目標とする体重が60kgの人で日常生活の労作が普通の人は、1800~2100kcalが適正な総エネルギー摂取量となります。
4-2.脂質の摂り過ぎに気を付ける
脂質の摂り過ぎは、動脈硬化を進行させる原因となります。
脂質のなかでも特に肉類に含まれる飽和脂肪酸は、血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪を増やす作用をもち、動脈硬化の進行リスクを高めるため、摂り過ぎないように注意することが必要です。
また、乳製品や魚卵、レバー、マヨネーズといった食品にはコレステロールが多く含まれていますので、過剰摂取しないように意識することをおすすめします。
4-3.不飽和脂肪酸を積極的に摂取する
不飽和脂肪酸は、植物性油脂や魚の油に多く含まれ、悪玉コレステロールや中性脂肪を減らして動脈硬化を予防してくれます。
日常生活で不飽和脂肪酸を上手に摂取するには、料理の際に使う油をオリーブオイルや菜種油に変えたり、主食の割合を占める肉を減らして魚を増やしたりするのが有効です。
4-4.食物繊維を積極的に摂取する
食物繊維は腸内での脂質やコレステロールの吸収を抑制するはたらきがあるため、動脈硬化の予防が期待できます。
また、低カロリーで余分なナトリウムを排出する作用もあることから、高血圧や肥満予防にもなります。
食物繊維は野菜や、きのこ類、豆類、イモ類などに豊富に含まれていますので、意識して摂取することが大切です。
4-5.適度に運動する
動脈硬化予防のためには有酸素運動とレジスタンス運動をバランス良く行うのがおすすめです。
有酸素運動とは、筋肉への負荷が軽く長時間続けられるような運動です。ウォーキングや水中運動、サイクリングといった種目できつさをあまり感じない程度に30分間実施します。
レジスタンス運動とは、筋肉に負荷をかけた状態で一定の運動動作を繰り返すことです。腕立て伏せなどの自分の体重を利用した方法と、マシントレーニングなどで行う方法があります。
どちらも週3回以上を目標に実施すると効果が期待できます。
4-6.適度な飲酒量を守る
過度の飲酒は脂質異常症や高血圧を招き、動脈硬化を進行させてしまうため、お酒を飲む際は適量に留めることが大切です。
厚生労働省によると、適切な1日のアルコール摂取量は20g程度とされています[4]。
ビール500ml、ウイスキー60mlであればアルコール20g、清酒180mlであればアルコール22gとなりますので、目安にすると良いでしょう。
ただし、アルコールへの耐性は性別、年齢、体力などにより個人差があります。特に女性や高齢者、飲酒で頭痛や吐き気などを感じやすい人などは、目安よりも少ない量で考える必要があります。
[4] 厚生労働省「アルコール」
4-7.禁煙する
禁煙をすることで動脈硬化の予防効果が期待できます。予防効果は禁煙を開始してからすぐに現れ、禁煙期間が長くなるほどリスク低下が期待できます。
ただし、喫煙の本数を減らす、あるいはニコチン・タールの含有量を減らすといった対策では十分な効果は期待できません。
最近は禁煙補助剤、禁煙外来が気軽に利用できるようになっています。喫煙者の方で動脈硬化のリスクがある場合は、禁煙成功率を高めるために利用を検討してみてはいかがでしょうか。
5.動脈硬化の原因のまとめ
動脈硬化が進行すると重大な脳心血管疾患のリスクが高まります。
脳心血管疾患は急死に至る場合もあり、自覚症状がほとんどない疾患もありますので、症状が出ていない段階からしっかりと予防に取り組むことが大切です。
動脈硬化を予防し進行を遅らせるためのポイントは生活習慣を改善することです。
本記事でご紹介した七つのポイントを参考に生活習慣を改善し、動脈硬化の予防に取り組んでみませんか。
この記事の監修者
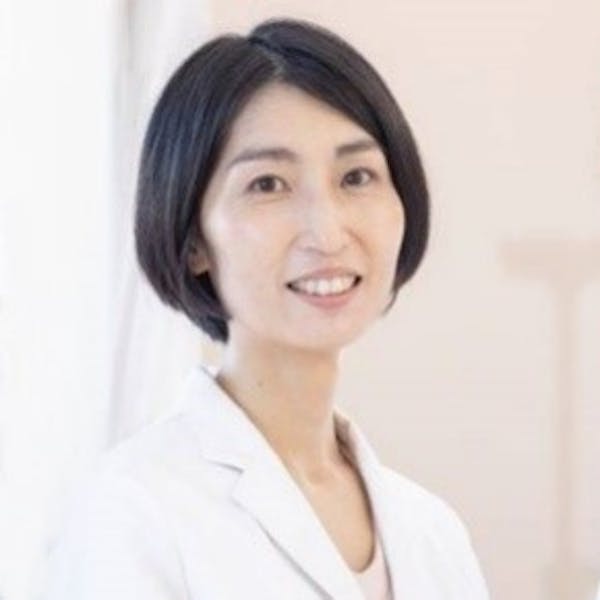
内科認定医・がん治療認定医
【経歴】
国立大学医学部医学科卒業後、公立病院にて初期研修の2年を終了後、3年目からはがん治療を専門としながら幅広く内科疾患の診療に従事。治療が必要となる前の生活習慣の改善、また病気についての正しい知識が大事であることを実感し、病気についての執筆活動にもあたっている。


































