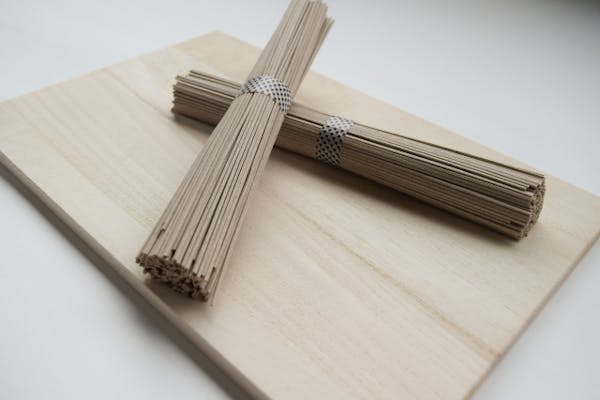そばのタンパク質含有量は?その他の栄養素やおすすめの食べ方も紹介
「そばにはどれくらいタンパク質が含まれているのかな?」
「そばは体に良さそうだけど、カロリーはどれくらいあるんだろう?」
と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
そばをはじめとする麺類は、ご飯やパンと並び私たちの主食となる食品です。
穀類であるそばには炭水化物(糖質)はもちろん、タンパク質やビタミン・ミネラルなどさまざまな栄養素が含まれています。
またルチンというポリフェノールの一種を含んでいることも特徴の一つといえるでしょう。
この記事ではそばに含まれるタンパク質の量やその特徴、そばに含まれるその他の栄養素、そばから効率良く栄養を摂取する食べ方などについて解説します。
そばの特徴を知り、食生活にぜひ取り入れてみてくださいね。
1.そばに含まれるタンパク質の量
「そばのタンパク質ってどのくらいあるんだろう?」
このように思ったことのある方もいらっしゃるでしょう。
穀物であるそばに含まれる栄養素の主体は糖質ですが、タンパク質も含まれています。
スーパーなどで販売されているそばには「乾麺(干しそば)」と「生麺」があり、一般的には乾麺を購入することが多いかもしれませんね。
乾麺のそばと生麺のそば、それぞれのゆでる前後のタンパク質の含有量は以下のとおりです。
【そば100g当たりのタンパク質含有量】
| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |
|---|---|---|
| 干しそば | 乾麺 | 14.0g |
| 干しそば | ゆで | 4.8g |
| そば | 生麺 | 9.8g |
| そば | ゆで | 4.8g |
| 半生そば | - | 10.5g |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
タンパク質は肉や魚に豊富に含まれているイメージですが、そばにも含まれていることが分かりますね。
タンパク質は炭水化物や脂質とともにエネルギーをつくり出す他、筋肉や臓器、皮膚などの材料となるなどヒトの体に必須の栄養素です。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、タンパク質の1日当たりの摂取推奨量を成人男性で60g~65g、成人女性で50gとしています[2]。
2.そばと他の主食の栄養の違い
ご飯やパン、そばをはじめとする麺類は食事の基本となる主食に該当する食べ物です。
ここでは主食の代表格であるご飯、そばとよく比較されるうどんそれぞれのカロリーやタンパク質の量をそばと比較してみましょう。
2−1.ご飯との違い
ご飯にもそばと同様、糖質やタンパク質が含まれています。
そばとご飯のカロリーや糖質、タンパク質、脂質の含有量を比較してみましょう。
【そばとご飯(精白米)のタンパク質、脂質、糖質の含有量およびカロリー】
| 食品名 | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| そば(乾麺)100g | 65.9g | 14.0g | 2.3g | 344kcal |
| そば(乾麺/ゆで)100g | 21.5g | 4.8g | 0.7g | 113kcal |
| ご飯(精白米)100g | 34.6g | 2.5g | 0.3g | 156kcal |
| ご飯(精白米)茶碗1杯(約150g) | 約51.9g | 約3.8g | 約0.5g | 約234kcal |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
ご飯100gとゆでたそば100gで比較すると、そばにはご飯の倍近いタンパク質が含まれています。
つまり、そばはご飯よりもタンパク質が摂れる食品であるといえます。
2−2.うどんとの違い
次はうどんとの違いを見てみましょう。
そばとうどんは同じ麺類ということで、タンパク質の他カロリーや糖質なども比較されがちな食品ですよね。
どちらも乾麺で比較してみると以下のようになります。
【そばとうどん100g当たりのタンパク質、脂質、糖質の含有量およびカロリー】
| 食品名 | 糖質 | タンパク質 | 脂質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| そば(乾麺) | 65.9g | 14.0g | 2.3g | 344kcal |
| うどん(乾麺) | 69.9g | 8.5g | 1.1g | 333kcal |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
タンパク質含有量はそばの方が多いことが分かります。
またその他のエネルギー産生栄養素を比較すると、糖質はそばの方がやや少ない半面、脂質はそばの方がやや多く、カロリーには大きな差がないことが分かります。
そばのタンパク質含有量が多いのは、そばの原材料であるそば粉とうどんの原材料である小麦粉(中力粉)のタンパク質含有量の差によるものと考えられます。
そば粉と小麦粉(中力粉)のタンパク質含有量は以下のとおりです。
【そば粉と小麦粉(中力粉)100g当たりのタンパク質含有量】
| 食品名 | タンパク質含有量 |
|---|---|
| そば粉(全層粉) | 12.0g |
| 小麦粉(中力粉) | 9.7g |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
つまり、そばのタンパク質の多さはそば粉に由来するものであるということになりますね。
3.そばに含まれるタンパク質の特徴
そばのタンパク質には、他の穀類に不足しがちな「必須アミノ酸」の一つ「リシン(リジン)」が豊富に含まれています。
リシンはホルモンや酵素などの成分として利用される他、体の成長などにも関わるなど重要な役割を担うアミノ酸です。
しかし、私たちが主に主食とする米や小麦のタンパク質にはリシンが不足していることもあってか、必須アミノ酸のなかでは最も不足しやすいといわれています。
動物性食品や大豆製品などのタンパク質にもリシンは含まれていますが、主食としてそばを取り入れることでリシンを補うことができますね。
4.そばに含まれるその他の栄養素・成分
そばの原材料のそば粉にはタンパク質の他、ビタミンやミネラルなどが含まれています。
ここではそばに含まれるたんぱく質以外の栄養素や成分をご紹介します。
4−1.食物繊維
そばには「食物繊維」が含まれています。
食物繊維とは人間の消化酵素で消化できない成分の総称で、私たちの健康に良い影響を与えてくれる栄養成分です。
食物繊維は便通を整える効果で知られる他、脂質や糖、食塩の主成分であるナトリウムなどを体の外へ排出するはたらきがあることから生活習慣病の予防や改善に役立つ効果も期待されています。
【そば(乾麺)100g当たりの食物繊維含有量】
| 食品名 | 食物繊維(総量) |
|---|---|
| そば(乾麺) | 3.7g |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
そばを食べることで食物繊維が摂取でき、便秘や生活習慣病の予防につながるのはうれしいポイントですね。
4−2.ビタミンB群
ビタミンB群は、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類の水溶性ビタミンです。
ビタミンB群は、主に食事から摂取した栄養素からエネルギーをつくり出すことに関わっています。
そのため不足するとエネルギーが十分につくられず、疲労を感じる原因となってしまうのです。
ビタミンB群のうち、そばから摂取できる栄養素は以下のとおりです。
| 食品名 | ビタミンB1 | ビタミンB6 | ナイアシン(当量) | パントテン酸 |
|---|---|---|---|---|
| そば(乾麺) |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
ビタミンB群が含まれるそばを食べることは、疲れにくい体づくりに役立つ可能性があるのですね。
4−3.マグネシウム
マグネシウムもミネラルの一種です。
神経伝達や筋肉収縮、血圧や体温の調整などに加え、体内で起こるほとんどの反応に関わる重要な栄養素です。
またカルシウムと密接な関係にあり、骨の健康にも関与しています。
【そば(乾麺)100g当たりのマグネシウム含有量】
| 食品名 | マグネシウム |
|---|---|
| そば(乾麺) | 100mg |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
4−4.ルチン
そば粉にはルチンが含まれています。
ルチンはビタミンと似た作用を持つ「ビタミン様物質」の一種で、抗酸化作用を持つ「抗酸化物質」です。
抗酸化物質には体内で合成されるもののほか、食品から摂取できる「ポリフェノール」や「カロテノイド」などがあります。
ルチンは抗酸化物質のうち、緑茶の「カテキン」や大豆の「イソフラボン」などと同じポリフェノールに分類される成分です。
強い抗酸化作用を示し、毛細血管の強化や高血圧予防のほか、血液を固まりにくくする、いわゆる血液をさらさらにする効果が期待されています。
ルチンは体内に増え過ぎた活性酸素を減らすことで、老化防止に役立つ成分なのですね。
5.そばの栄養を効率良く摂る食べ方
そばにはタンパク質の他、ビタミンやミネラル、抗酸化作用のある成分などが含まれています。
これらの栄養成分の効果を十分に得るためには、押さえておきたいポイントがあります。
ここでは、そばに含まれる栄養を効率良く摂取する方法について見ていきましょう。
5-1.そば粉の配合割合の高いものを選ぶ
タンパク質をはじめ、そばの栄養を効率良く摂取するには「そば粉の割合」に注目してみましょう。
そばにはそば粉のみで作られている「十割そば」もありますが、実は一般的なそばはそば粉と小麦粉から作られています。
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」中のそばの栄養価も、そば粉35%、小麦粉65%の割合で作られたそばのものであることが成分表の「備考欄」に掲載されています[5]。
小麦粉よりもそば粉の方がタンパク質の含有量が多いことを考えれば、そば粉の割合が高ければ高いほどタンパク質の含有量も多くなるといえるでしょう。
これはタンパク質に限らず、そば粉に含まれているルチンにもいえることです。
そば粉の割合を示す表示を確認し、なるべくそば粉の割合が多いものを選ぶことで、そばに含まれる栄養を効率良く摂取できるでしょう。
5-2.そば湯を飲む
そば屋などでは、よくそばと一緒に「そば湯」が提供されますよね。
そば湯とはそばをゆでた後のお湯のことで、このそば湯を飲むことでそばの栄養素が効率良く摂取できるのです。
そばに含まれるビタミンB群やカリウム、ルチンは水に溶けやすい性質があるため、そば湯にはこれらの栄養素が溶け出しています。
なかでもビタミンB1はゆで湯への流出が多いことが分かっています。
そばの栄養素を十分に取り入れたいと考えるなら、そば湯を飲むようにするのが効率的ですね。
ただし、そば湯を飲む際にそばつゆを入れ過ぎると塩分の過剰摂取につながるため、その点は注意してください。
6.そばのタンパク質についてのまとめ
そばには、同じ主食に分類されるご飯やうどんよりも多くのタンパク質が含まれています。
そばのタンパク質の特徴は、他の穀類に不足している必須アミノ酸のリシンを多く含んでいることです。
また、タンパク質の他にそばに含まれている栄養成分としては食物繊維やビタミンB群、カリウム、マグネシウム、抗酸化物質ルチンなどがあります。
このようなそばの特徴は、原材料のそば粉に由来しています。
そのため、そばの栄養を効果的に摂取したいという方はそば粉の配合割合の高いものを選ぶと良いでしょう。
また、そばに含まれるビタミンやミネラル、ルチンは水溶性であるため、そば湯を飲むことで効率良く摂取できます。
体にとって必要な栄養素を適切に摂取するために、そばも主食として日々の食事にうまく取り入れてみてくださいね。