「動脈硬化を予防・改善する方法ってあるの?」
「健康診断でコレステロール値高めと診断された。次回までに何とかしたい……」
コレステロール値が高くなると、動脈硬化が進行し、内臓や足などに必要な血液が十分に行き渡りにくくなります。
動脈硬化が起こる部位によっては狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす恐れもあり、早めに対策を行うことが大切です。
この記事では、動脈硬化の予防や改善に役立つ5つの方法とポイントを紹介します。健康診断でコレステロール値が高かった、動脈硬化のリスクがあると言われた方は、参考にしてみてください。
1.動脈硬化を予防・改善する方法 1.肥満を解消する
肥満のなかでも、胃や腸などの内臓の周りに脂肪が付く内臓脂肪型肥満は、生活習慣病を合併しやすいといわれています。
内臓脂肪型肥満に生活習慣病が重なるとメタボリックシンドロームになりやすく、それによって動脈硬化が進行します。
動脈硬化が進むと、狭心症や心筋梗塞といった心疾患、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患のリスクが高まるため、まずは肥満を解消することが大切です。
とくに現代では食生活が豊かになったことで、食事から摂取するエネルギー量が増えてきているといわれています。加えて、車や公共交通機関(バスや電車など)を使った移動が多く、運動量は減少傾向にあるといえるでしょう。
摂取エネルギーが消費エネルギーを上回りやすい状況から、肥満で悩む人が増えているのが現状です。
とはいえ、肥満を解消したいと思ってダイエットなどに取り組んだものの、なかなか痩せられないと感じている方もいるのではないでしょうか。
そんな方のために、肥満を解消するためのポイントをご紹介します。
1-1.減量は3~6カ月で考える
減量を成功させるには、無理なダイエットをしないのがポイントです。
短期間で体重を落とそうとして食事や摂取エネルギーの量を極端に減らすと、すぐに効果が出やすいものの、継続が難しく、結局はリバウンドしやすいからです。
体重の減少速度はゆっくりでも、着実に痩せやすい生活を続ける方が肥満解消につながります。
また、肥満解消のためには、3~6カ月くらいのスパンをかけて、体重あるいはウエスト周囲長を3%以上減少させるのを目標とすることが推奨されています[1]。
例えば、体重が80kgの人であれば、3~6カ月間で2.4kg以上減量するのが目安です。かなり少なく感じるかもしれませんが、無理のないペースで少しずつ体重を減らしていくようにしましょう。
1-2.総エネルギー摂取量を適正にする
1日のエネルギー摂取量が消費エネルギーを上回ると肥満の原因になります。これ以上体重を増やさないように総エネルギー摂取量を制限することが大切です。
総エネルギー摂取量は、日常生活での活動量をもとに以下の計算で求められます。
例えば、目標とする体重が60kgで、1日にほとんど体を動かす機会がない人の場合は以下のとおりです。
60(kg)×20~30=1,200~1,800kcal
この場合、1日の総エネルギー摂取量を1,200~1,800kcalに留めることで、目標体重に近づけるでしょう。
2.動脈硬化を予防・改善する方法 2.食生活の見直し
普段の食生活は、動脈硬化の進行や改善、予防に大きく関連します。脂質の摂り過ぎや肉中心の食事といった食事は、中性脂肪やコレステロール値が増えて血液がドロドロになりやすくなります。
動脈硬化のリスクがある、コレステロール値が高いと診断された方は、普段の食事を見直してみましょう。
動脈硬化を予防・改善につながる食生活のポイントをご紹介します。
2-1.飽和脂肪酸の摂り過ぎに気を付ける
脂質の摂り過ぎは血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪の増加につながり、動脈硬化を進行させるほか、肥満などの原因となります。
とはいえ、脂質そのものがすべて体に悪いというわけではありません。
脂質は体に必須とされている三大栄養素の一つです。また、脂質を構成する脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2種類があり、不飽和脂肪酸は血液中のコレステロール値を下げるなど体に良いはたらきをすることが分かっています。
しかし、動物性脂肪に多く含まれている飽和脂肪酸は、血液中のコレステロールや中性脂肪を増やすため摂り過ぎないように注意しましょう。
【飽和脂肪酸が多く含まれる食品と100g当たりの含有量】
| 飽和脂肪酸が多く含まれる食品 | 100g当たりの飽和脂肪酸の含量 |
|---|---|
| バター(食塩不使用) | 52.43g |
| 豚ロース(脂身) | 34.40g |
| 牛リブロース(脂身) | 32.03g |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 24.98g |
| マーガリン(家庭用・有塩) | 23.04g |
| チェダーチーズ | 20.52g |
文部科学省「日本食品標準成分表2020年度版(八訂)」をもとに執筆者作成
動脈硬化の予防・改善にはこれらの食品を控えることが大切です。
2-2.不飽和脂肪酸を含む食材を積極的に取り入れる
脂肪酸の一つである不飽和脂肪酸は、血液中の中性脂肪、またコレステロールを低下させ、動脈硬化の予防につながるといわれています。
不飽和脂肪酸は、植物や魚の脂に多く含まれており、人間の体内で合成することができません。そのため、食事で積極的に摂取することが求められます。
代表的な不飽和脂肪酸は、オリーブ油や菜種油などに含まれるオレイン酸、青魚に豊富といわれているDHAやEPAなどです。
炒めものなどで油を使うときは、オリーブ油や菜種油を使うように心掛けると、不飽和脂肪酸の摂取量を増やすことができるでしょう。
また、イワシやサンマなどの青魚を積極的に摂ると、DHAやEPAを摂取することができます。煮付けや塩焼きといった和食のほか、ハーブをまぶしてオリーブ油でソテーするなど洋風アレンジも取り入れると、変化を楽しめるでしょう。
1日1食は魚を取り入れたいものの、肉類を食べてはいけないというわけではありません。飽和脂肪酸が多く含まれているとはいえ、肉は体に必要なタンパク源となります。
「肉だけ」「魚だけ」ではなく、肉と魚をバランス良く摂取するのが、健康な体づくりには大切です。
2-3.食物繊維を積極的に取り入れる
食物繊維には、脂質や糖、ナトリウムを体外に排出する作用があるといわれています。つまり、これらの摂り過ぎによる肥満を防いでくれるはたらきがあるのです。
食物繊維が体に良いと分かっていても、「摂取量を増やすのが難しい」と感じている方は、食事に工夫することで摂取量を増やすことができます。
例えば、主食を白米から玄米や胚芽米、麦飯などに変えます。パンであれば全粒粉のパン、麺類はラーメンやうどんではなく蕎麦を食べると食物繊維の摂取量を増やすことができるでしょう。
また、食事1回ずつに食物繊維が豊富な野菜やきのこ、海藻、こんにゃくなどを食べるのもおすすめです。豆類にも豊富なので、納豆も取り入れると良いでしょう。
ただし、食物繊維を含むとはいえ果物の摂り過ぎには注意が必要です。果物に含まれる果糖の大量摂取はエネルギーの過剰摂取となり、肥満や中性脂肪、インスリン抵抗性の増大、2型糖尿病の発症につながるといわれています。
3.動脈硬化を予防・改善する方法 3.適度な運動を取り入れる
適度な運動は動脈硬化の予防・改善に効果が期待できます。
ただし、無理な運動は筋骨格系障害をきたす可能性があり、また心血管疾患の既往歴や高リスク者の場合は急激な運動で負担をかけすぎると突然死や心血管事故が起こる恐れがあります。
加えて、重症網膜症を有する糖尿病患者の方や血糖値が著しく高い方などは運動が禁止されていることから、通院中、治療中の方は運動を始める前に主治医に確認することをおすすめします。
ここからは運動を取り入れる際のポイントを見ていきましょう。
3-1.有酸素運動を中心に実施する
動脈硬化の予防・改善を期待して運動を取り入れるなら、有酸素運動を中心に実施しましょう。
・運動の種類
血清脂質(血液の中に含まれる脂質)の改善に良いといわれている有酸素運動を行います。速歩、ジョギング、エアロビクス、水泳、サイクリングなど、自分にとって実施しやすい運動を選んでみましょう。
・運動の強度
中強度以上の運動を目標にします。中強度とは「楽~ややきつい」と感じるくらいの強度です。
・運動の頻度・時間
毎日30分以上を目標に運動を行います。連続で30分が難しければ、朝10分、夕方20分というように合計で30分になるようにすると良いでしょう。
毎日実施するのが難しければ、最低でも週に3日は運動するようにおすすめします。
3-2.レジスタンス運動を週2~3回継続的に行う
レジスタンス運動とは、腕立て伏せやスクワットのように筋肉に抵抗をかける動作を繰り返し行う運動のことです。
やり方には大きく二つあり、腕立て伏せやスクワットのような自体重を利用して行う方法と、ダンベルやマシンなどの器具を使った方法があります。
いずれにしても最大重量の50~85%重量でできる最大反復数の運動(平均だと12回程度)を、1~2分程度の休憩をはさみつつ1種目当たり1~5セット実施すると良いでしょう[3]。
レジスタンス運動は週に2~3回継続的に実施するのが望ましいとされています。
3-3.運動はハードルが高いと感じたら・・・
運動に挑戦したものの、「きつくて続けられない……」と感じている方もいるかもしれません。
そんな方は、まずは日常生活のなかで運動量を増やすことから始めてみましょう。
例えば、電車通勤なら1駅手前で下車して歩く、思い切って自転車通勤にしてみるといったことができるかもしれません。また、職場や駅ではエレベーターを使わずに階段を使うよう意識するだけで、自然と運動量を増やすことができます。
家庭でも掃除などをこまめに行うよう努めて、なるべく体を動かすことができるでしょう。加えて、テレビを見ながら腕立て伏せやスクワットをしたり、ストレッチをしたりすることもできます。
近所の買い物であれば、車を使わずに歩くようにするのもおすすめです。
4.動脈硬化を予防・改善する方法 4.多量の飲酒をしない
適量のお酒には血液の流れを良くし、動脈硬化の予防に役立つといわれています。ただし、お酒の飲みすぎやおつまみの内容によっては中性脂肪の増加につながり、動脈硬化の原因となります。
また、高血圧や糖尿病、心疾患、脳血管疾患、膵炎(すいえん)などの原因にもなるため「適量」の摂取が重要です。
ここでは、適切な飲酒量を守るためのポイントをご紹介します。
4-1.飲酒は適量を守る
お酒は飲み過ぎないように注意し、適量を守りましょう。また、週に1回は肝臓を休ませるために休肝日を設けるのがおすすめです。
1日に摂取するアルコールの適量は約20g程度が推奨されています。アルコール量の目安は、ビールであれば中瓶1本(500ml)、ウイスキーならダブル1杯(60ml)が20g、清酒1合(180ml)は22gです[4]。
これを超えると、適量を超えて飲み過ぎになるので注意しましょう。
ただし、女性や高齢者、飲酒によって頭痛や吐き気などの症状が出やすい方は、この量よりも少なめに留めるようにしましょう。
[4]厚生労働省「アルコール」
4-2.おつまみの選び方も工夫しよう
お酒を飲む際には、おつまみの選び方も工夫しましょう。
定番の唐揚げやフライドポテト、ソーセージなどのおつまみは脂質や塩分が多く、かつ高カロリーです。動脈硬化の予防・改善を目指すなら、控えるようおすすめします。
代わりに野菜や海藻類を使ったおひたしや和え物、サラダ、酢の物などをおつまみにすると、アルコールによって失われやすいビタミンやミネラルを補給できます。
加えて、アルコールの分解にはたんぱく質が消費されるため、高たんぱく質の豆類を使った冷や奴や枝豆などのおつまみを選ぶのも良いでしょう。低エネルギーの刺身もおつまみにぴったりです。
5.動脈硬化を予防・改善する方法 5.禁煙する
喫煙は動脈硬化の進行を促すので、禁煙は予防や改善につながります。
とはいえ、これまでタバコをやめようと努力したことがあるものの、「うまくいかなかった……」という方もいるかもしれません。
ここでは、禁煙に真剣に取り組むべき理由と一人での禁煙が難しい場合の対処法をご紹介します。
5-1.禁煙の効果は開始すぐに期待できる
禁煙は動脈硬化性疾患の進行や罹患、死亡リスクを低下させるといわれています。効果は禁煙を開始してすぐに現れ、禁煙期間が長くなればなるほどリスクが低下するとされています。
喫煙者のなかには、「タバコの本数を減らせば良いのでは?」と感じる方もいるのではないでしょうか。
残念ながら、タバコの本数を減らすだけでは脳心血管疾患のリスク低下は見込めません。低ニコチンや低タールのタバコに変えても同様です。
加えて、一度禁煙した人が再度喫煙した場合はリスクが上昇することが分かっており、動脈硬化の予防・改善を期待するなら禁煙が必須といえます。
5-2.一人での禁煙が難しい場合は・・・
「禁煙に取り組んだものの、うまくいかなかった」
「タバコはやめられない……」
このように感じている方もいるかもしれません。
禁煙が難しい場合は、ニコチンガム、ニコチン貼付薬、バレニクリンなどの禁煙補助薬を使用してみましょう。
また、禁煙外来を受診してみるのも一つの手です。日本では一定の条件を満たせば禁煙治療(12週間にわたる)が保険適用になるため、そうしたものを上手に活用しましょう。
6.動脈硬化を予防・改善する方法のまとめ
現時点では、動脈硬化そのものの治療法は確立されておりません。
動脈硬化の危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙にアプローチする治療を行うのが主な治療法となります。
動脈硬化そのものを治すことはできないため、予防に努めること、また動脈硬化を進行させないように努力することが大切です。
コレステロール値が高い方、動脈硬化のリスクが高い方は、この記事で紹介した動脈硬化を予防・改善する五つの方法を実践してみてください。
この記事の監修者
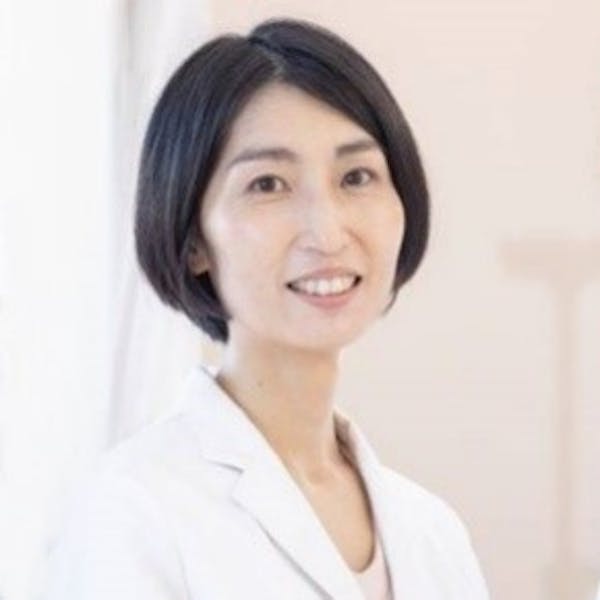
内科認定医・がん治療認定医
【経歴】
国立大学医学部医学科卒業後、公立病院にて初期研修の2年を終了後、3年目からはがん治療を専門としながら幅広く内科疾患の診療に従事。治療が必要となる前の生活習慣の改善、また病気についての正しい知識が大事であることを実感し、病気についての執筆活動にもあたっている。






































