「健康診断で、血圧が160/100mmHg以上もあった……」
「血圧が160/100mmHg以上もあると、病気になるリスクは高いの?」
健康的で長生きするためには、血圧の値も重要です。血圧が高いと、さまざまな病気を引き起こすリスクが上がります。なかには命に関わる危険な病気もあるため、高血圧についてきちんと知っておきましょう。
この記事では、血圧160/100mmHg以上で起こる症状とリスクについて解説します。
1.血圧160/100mmHg以上はⅡ度・Ⅲ度高血圧に分類される
血圧の正常値は、診察室血圧が<120かつ<80、家庭血圧が<115かつ<75です[1]。
また、診察室血圧が160~179または100~109mmHg、家庭血圧が145~159または90~99は「Ⅱ度高血圧」に分類されます。
Ⅱ度高血圧以上の数値は「Ⅲ度高血圧」に分類されます。自身の血圧が160/100mmHg以上の場合、できる限り早めに受診すると良いでしょう。
2.血圧160/100mmHg以上で起こる症状
診察室血圧が血圧160/100mmHg以上の場合はⅡ度高血圧に分類されるものの、基本的に症状はみられません。ただし、二次性高血圧の場合や合併症、臓器障害がある場合は以下のような症状が表れることがあります。
2-1.二次性高血圧の場合にみられる症状
原因不明の高血圧を「本態性高血圧」と言います。高血圧症とされる全体の9割が本態性高血圧といわれており、主に遺伝的要素や生活習慣などによって起こります。
二次性高血圧とは特定の原因がある高血圧症のことです。二次性高血圧に見られる症状は主に以下が挙げられます。
- 体重の増加
- メタボリックシンドローム関連因子(脂質代謝異常や耐糖能)
- 夜間頻尿
- 夜間呼吸困難
- 早朝の頭痛
- 昼間の眠気
- 睡眠時のいびきや無呼吸
- 集中力の低下
2-2.臓器障害・合併症を生じている場合にみられる症状
臓器障害や合併症を発症している場合にみられる症状としては、以下が挙げられます。
- 脳血管障害がある場合:一過性脳虚血発作,筋力低下,めまい,頭痛,視力障害
- 心臓疾患がある場合:呼吸困難,体重増加,下腿浮腫,動悸,胸痛
- 腎臓病がある場合:多尿,乏尿,夜間尿,血尿
- 末梢動脈疾患がある場合:間欠性跛行,下肢冷感
なお、上記の症状は二次性高血圧の方や高血圧で臓器障害がある方すべてに起こり得ます。高血圧で上記の症状に該当する場合は、できる限り早めに受診することをおすすめします。
3.血圧160/100mmHg以上になる原因
高血圧の対策・改善をする前に、なぜ血圧が上がるのか、原因を特定することが大切です。ここでは、血圧160/100mmHg以上の方へ向けて、血圧が上昇する生活要因をご紹介します。
下記に当てはまる方は、今日から生活習慣を見直しましょう。
3-1.塩分の多い食生活をしている
食塩の過剰摂取は血圧上昇と深い関係があります。塩分を多く摂るとその分血液中の塩分濃度を下げるために水分摂取が増えます。結果として血液量が増加し、心拍出量が増えて血圧が上がるのです。
日本では、1日の食塩摂取の目標量を男性7.5g未満、女性6.5g未満と定められています[2]。しかし、令和元年度の調査によると、日本人の食塩摂取量は平均10.1gで、男性10.9g、女性9.3gという結果が出ています[3]。
男女ともに、食塩の摂取量が多いことが分かりますね。
3-2.肥満でインスリンのはたらきが悪くなっている
インスリンは膵臓で作られるホルモンのことで、血液中の糖をコントロールし、一定に保つ役割があります。しかし、肥満になるとインスリンが適正に機能しなくなり、必要以上に分泌される恐れがあるのです。
インスリンは交感神経を刺激するため、過剰に分泌されることで血圧が上がる原因となります。肥満の人は高血圧になりやすいため、注意しましょう。
3-3.運動不足である
運動不足も高血圧の要因としてあげられます。また、運動不足は脳心血管病の発症リスクを高めるともいわれているため、注意しましょう。
3-4.喫煙をしている
タバコを吸うと、末梢血管が収縮して血圧が上がるといわれ、1本の紙巻きたばこの喫煙で15分以上の血圧上昇が持続することが示されています。
米国の研究結果で1日15本以上喫煙する人は高血圧の発症割合が高いことがわかっています。タバコの本数に関わらず、喫煙者は血圧上昇のリスクがあります。[4]。
3-5.お酒をよく飲む
お酒を多く飲むほど血圧が上昇しやすくなります。また、飲酒によって食欲が増進し、食事量が増えることでカロリー過多による肥満を招く恐れもあります。
3-6.ストレスが溜まっている
ストレスと血圧にも関係があります。血圧は交感神経と副交感神経がバランスを保って働くことで安定します。しかし、ストレスが溜まると血圧を上げる交感神経が優位になり、血圧が上がってしまうのです。
ストレスを溜める要因には仕事や家庭環境など人によってさまざまでしょう。運動や趣味などでリフレッシュし、その都度発散することが大切です。
3-7.睡眠不足が続いている
睡眠不足は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める要因の一つです。通常、睡眠時は血圧が下がるものの、睡眠不足の場合は血圧が高い状態が続くためです。
自分の体調に合った睡眠量、そして睡眠の質を上げることが大切です。
4.血圧160/100mmHg以上でリスクが高い疾患・病気
高血圧になるとどのような病気を引き起こすリスクがあるのでしょうか。一般的に血圧が120/80mmHgを超えて血圧が高くなればなるほど、脳心血管病と慢性腎臓病のリスクが高くなると言われています[5]。
また脳心血管病のリスクについては、血圧が160/100mmHgを超えると他に予後影響因子がなくても中等リスク以上となるとされています。
病気を早期発見または予防するためにも、普段から血圧を測定することが大切です。また、高血圧が続くようであれば、早めに受診することをおすすめします。
以下は診療室血圧にもとづいた脳心血管病リスク層の表です。
| リスク層/血圧分類 | 高値血圧(130-139/80-89mmHg) | I度高血圧(140-159/90-99mmHg) | Ⅱ度高血圧(160-179/100-109mmHg) | Ⅲ度高血圧(≧180/≧110mmHg) |
|---|---|---|---|---|
| リスク層第一種(予後影響因子がない) | 低リスク | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |
| リスク層第二種(年齢が65歳以上、男性、脂質異常症、喫煙のいずれかに該当する場合) | 中等リスク | 中等リスク | 高リスク | 高リスク |
| リスク層第二種(脳心血管病既往、非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿のあるCKDのいずれか、またはリスク第二種の危険因子が三つ以上該当する場合) | 高リスク | 高リスク | 高リスク | 高リスク |
4-1.脳卒中
脳卒中とは脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の血流に障害を受ける病気のことです。脳卒中になると「うまく言葉が話せなくなる」「手足が痺れる、動けなくなる」「うまく立ったり、歩けなくなったりする」といった症状が起こります。
脳卒中は、症状によって「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」と分けられます。ここでは、それぞれの症状や特徴についてみていきましょう。
4-1-1.脳梗塞
脳の血管が詰まったり細くなったりして血流が途絶え、脳が壊死してしまう病気です。脳卒中の大半を占めるのが脳梗塞といわれており、脳梗塞になると、血流の途絶えた血管が支配していた範囲により、言語障害や半身麻痺、認知機能の低下といった症状が現れます。
脳の血管が詰まって数時間が経過すると脳細胞が壊死し、元に戻ることはありません。しかし、脳の血管が詰まっても数時間以内に血流を再開できれば脳卒中の症状を軽くできる可能性があります。
脳梗塞には血管の詰まり方によって以下の三つのタイプに分類できます。
- ラクナ梗塞:脳血栓のなかでも脳の深い部分を流れている細い血管が詰まる脳梗塞
- アテローム血栓性脳梗塞:脳や頸部の動脈硬化によって血管を閉塞して起こる脳梗塞
- 心原性脳塞栓症:心臓でできた血栓が血流に乗って脳の血管に詰まる脳梗塞
4-1-2.脳出血
脳出血は脳の血管が破れ、脳内出血する病気です。脳内出血した血液は時間が経つと血腫になり、さらに時間が経過すると脳にむくみが出始めます。
脳梗塞と同様に、言語障害になったり、半身麻痺が起こったりします。
4-1-3.くも膜下出血
くも膜下出血は、「脳動脈瘤」と呼ばれる脳の動脈にできたコブが破裂することで起こる病気です。
くも膜下出血になると、激しい頭痛や意識障害などの症状が起こります。脳卒中のなかでも死亡率が高く危険な病気ですが、脳動脈瘤の破裂は未然に防止することが可能です。
4-2.心臓病
心臓病は心臓の機能や働きに異常が生じて起こる病気の総称で、「冠動脈疾患」「心肥大」「心不全」などが該当します。
ここでは、心臓病について、症状や特徴などを解説します。
4-2-1.冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)
冠動脈疾患は心臓に血液を送る血管冠動脈が詰まったり狭くなったりして心臓に血液が行き渡らなくなる病気のことです。心臓が健全に活動するためには十分な酸素が必要ですが、冠動脈疾患になると血液が心臓に行き渡らなくなり心筋が酸素不足になります。心筋の働きが落ちることで、心臓の動きが悪くなり、心不全などの疾患を引き起こします。
冠動脈疾患は「虚血性心疾患」とも呼ばれ、狭心症や心筋梗塞も冠動脈疾患に該当します。
狭心症は心筋に供給される酸素が不足して起こる胸の痛みや圧迫感のことです。血管の一時的な狭窄などが原因であるため、安静にすると治ります。
一方、血管の血流が途絶えたままになってしまうのが心筋梗塞で、血管の支配する場所によっては、死に至る恐れもあるため、一刻も早い治療が必要です。
4-2-2.心肥大
心肥大とは心臓の筋肉が厚くなることです。高血圧になると、圧負荷の増大によって心肥大が起こりやすくなります。圧負荷とは、心臓から血液を全身に送り出すときに必要な圧力のことです。
そして心筋はその圧負荷に対応しようと自身の筋肉量を増大させるため、心肥大が起こります。心肥大になると心臓の収縮力が弱まり、心臓の機能が低下して全身に血液を送れなくなり、心不全を起こしやすくなります。
4-2-3.心不全
心臓の機能や働きが悪くなった状態のことです。心臓は全身に血液を送り届けるためのポンプとして活動しています。心不全になると呼吸困難や動悸、疲労感、体重増加などの症状が現れます。
4-2-4.慢性腎臓病
慢性腎臓病は、腎臓の障害、または腎臓機能の低下が3カ月以上続いている状態のことです。 腎臓の障害とは、たんぱく尿が出ること、血液中の老廃物である血清クレアチニンが尿へ排出されないことを指します。
慢性腎臓病の症状として、夜間尿や貧血、むくみ、息切れ、倦怠感などが現れます。
4-3.大動脈疾患
大動脈疾患とは、心臓から全身へと血液を送る血管(大動脈)に生じる病気のことです。大動脈は心臓から直接分岐する人間の血管のなかで最も太い血管で、血液循環の大元といえます。
ここでは大動脈疾患の種類と特徴について解説します。
4-3-1.大動脈瘤
大動脈瘤は大動脈がコブのように膨らんだ状態のことです。通常、大動脈は20~25mm程度ですが、30~40mm以上に膨らむと大動脈瘤になります。
大動脈瘤になっても症状が現れにくいため、「発見したときにはすでに大きくなっていた」というケースも少なくありません。症状として現れやすいのは、むせ込みや声が枯れる、胸部や背部の痛みなどが挙げられます。
こういった症状が現れた場合、大動脈瘤が破裂しやすくなるため注意が必要です。
4-3-2.急性大動脈解離
大動脈解離とは大動脈の中膜が破れ、そこに血液が入りこんで血管が裂けてしまう病気のことです。大動脈解離は前ぶれがなく突然起こり、胸部や背中に激痛が走ります。
なかには気を失ったり、しびれが生じて動けなくなったりする方もいます。急性大動脈解離は死亡率が非常に高い病気とされているため、早期治療が必要です。
4-3-3.下肢閉塞性動脈硬化症
下肢閉塞性動脈硬化症とは、足の動脈硬化によって下肢への血流が悪くなる病気のことです。下肢へ血液が行き渡らないことで栄養や酸素が不足し、さまざまな症状を引き起こします。
下肢閉塞性動脈硬化症の初期段階は指が青白くなったり、ふくらはぎの痛みが出てきたりします。また、次第に足の痛みがひどくなり、夜に眠れなくなることも少なくありません。最終的には下肢に潰瘍ができたり、黒く壊死したりします。
5.今日からできる高血圧の予防・改善方法
これまでご紹介してきた病気は高血圧が原因で発症する可能性があり、場合によっては生命に関わる重大な病気もあります。
血圧が気になる方は、今からでも生活習慣を見直し、改善しましょう。ここでは今日からできる高血圧の予防・改善方法を三つ詳しく解説します。
5-1.食生活を見直す
高血圧の原因の一つに塩分の過剰摂取や飲酒が挙げられます。塩分を控えた健康的な食生活を送ることで、高血圧を予防や治療につながるでしょう。
まず食事では以下四つのポイントを意識してみてください。
- 減塩
- 野菜・果物の摂取
- 体重のコントロール
- 節酒
食塩摂取の約7割が調味料類を占めるといわれているため、普段から塩分の量を控えたり、香辛料や酸味、薬味を上手く活用して味付けしたりすることが大切です。
減塩におすすめのポン酢 >
また野菜や果物には「カリウム」と呼ばれる栄養素を多く含んでおり、降圧効果に期待できます。バナナ1本とオレンジ1個程度を目安に食べることが推奨されています。
そのほか、体重を1kg減らすことで収縮機血圧は約1.1mmHg、拡張期血圧は約0.9mmHg低下すると推定されています[6]。肥満の方は適正体重を目指し、毎日の食事は腹八分目となるようコントロールしてみてください。
お酒も血圧を上げる原因の一つであるため、飲酒はほどほどにし、毎日お酒を飲む方は週に1日以上は休肝日を設けるようにしましょう。飲酒制限するだけで1〜2週間のうちに降圧するといわれています。
厚生労働省が掲げるアルコールの適量は、1日約20g程度です。目安としてはビール(500ml)、ウイスキー(60ml)で20g、清酒(180ml)で22gです[7]。この量を超えるアルコールを摂取している場合は、高血圧のリスクが高まるため注意しましょう。
5-2.適度な運動をする
有酸素運動は降圧に効果的といわれています。有酸素運動をすることにより、収縮期血圧で2~5mmHg、拡張期血圧で 1~4mmHgの低下が期待できます[8]。
運動は速歩やステップ運動、スロージョギング、ランニングなどの有酸素運動をしましょう。運動強度は「ややきつい」と感じる程度で、毎日30分以上が理想的とされています。また有酸素運動に加えてレジスタンス運動やストレッチ運動を組み合わせることも推奨されています。
5-3.禁煙する
禁煙は、高血圧予防において非常に重要です。しかし、喫煙習慣のある方が禁煙するのは容易なことではなく、挫折してしまう方も多くいます。
一人での禁煙が難しい場合は、禁煙補助薬を利用するか、保険診療で禁煙指導を受けることも検討してみてください。
6.高血圧の症状のまとめ
血圧が160/100mmHg以上あると、Ⅱ度・Ⅲ度高血圧に分類されます。高血圧になるとさまざまな病気を引き起こすリスクが上がり、薬が必要になったり生活への制限が必要となったりします。高血圧を防ぎ健康でいられるよう、日々の生活習慣を見直し、毎日血圧を測るようにしてみてください。
この記事の監修者
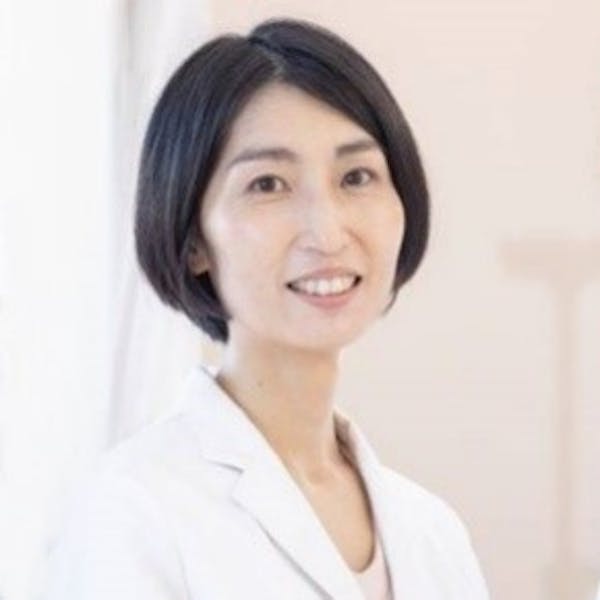
内科認定医・がん治療認定医
【経歴】
国立大学医学部医学科卒業後、公立病院にて初期研修の2年を終了後、3年目からはがん治療を専門としながら幅広く内科疾患の診療に従事。治療が必要となる前の生活習慣の改善、また病気についての正しい知識が大事であることを実感し、病気についての執筆活動にもあたっている。






































