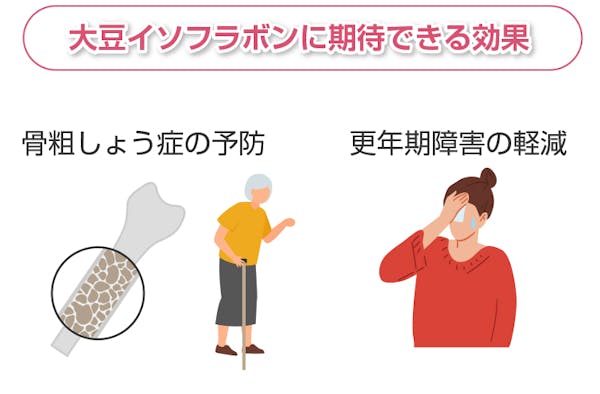大豆イソフラボンとは?はたらきや過剰摂取の影響、摂取目安量を解説
「大豆イソフラボンってどんな成分だろう……」
「大豆イソフラボンにはどんな効果があって、どれくらいの量を摂取するのが良いんだろう?」
大豆イソフラボンは体に良さそうなイメージがあるけど、実際にはどんな成分なのかよく知らないという方もいらっしゃるかもしれませんね。
大豆イソフラボンとは大豆や大豆胚芽に多く含まれる成分です。
女性ホルモンの一種であるエストロゲンと分子構造が近いことから、植物性エストロゲンとも呼ばれています。
大豆イソフラボンは骨粗しょう症の予防や改善などの体にとって良いとされる効果が期待できる一方、摂取する量に関する注意点もあります。
この記事では、大豆イソフラボンに期待できる効果や1日の摂取目安量などについて詳しく解説しています。
大豆イソフラボンを豊富に含んだ食品も紹介していますので、上手に食事に取り入れながらバランスの良い食生活を心掛けてくださいね。
1.大豆イソフラボンとは
「大豆イソフラボンってどんな成分なんだろう?」
大豆イソフラボンとはそもそもどんな成分なのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。
大豆イソフラボンとは大豆に多く含まれており、女性ホルモンの一種であるエストロゲンと分子構造が近いことから、植物性エストロゲンとも呼ばれています。
エストロゲンには第二次性徴を開始させて月経や妊娠を維持するはたらきなどがあります。
大豆イソフラボンは、ポリフェノールの一種であるフラボノイドに含まれる化合物です。
大豆イソフラボンには実は異なる構造のものがあります。
大豆イソフラボンは通常は糖が結合した構造をしていますが、糖が外れた構造のものを大豆イソフラボンアグリコンといい、大豆発酵食品の中に含まれています。
摂取した大豆イソフラボンは主に大豆イソフラボン配糖体という成分として体内に分布していますが、腸内細菌のはたらきにより大豆イソフラボンアグリコンとなり腸管から吸収されます。
体内で大豆イソフラボンアグリコンに変化することでエストロゲン受容体に結合し、エストロゲンに似た作用をもたらすといわれています。
2.大豆イソフラボンに期待できる効果
「大豆イソフラボンってどんな効果が期待できるんだろう?」
大豆イソフラボンには、どんな効果が期待できるのか気になりますよね。
植物性エストロゲンという別名を持つ大豆イソフラボンには主に「骨粗しょう症」の予防や改善と「更年期障害」の軽減という二つの効果が期待できるといわれています。
2-1.骨粗しょう症の予防
大豆イソフラボンには骨粗しょう症の予防や改善に効果が期待できると考えられています。
大豆イソフラボンにはエストロゲンが減少したときに代わりとなってエストロゲンに似たようなはたらきをするといわれています。
エストロゲンには骨をつくる細胞と壊す細胞のはたらきのバランスを調整するという機能があります。
そのため、エストロゲンの分泌量が低下するとこの機能がうまくはたらかなくなり、骨を壊す細胞のはたらきが強まります。
エストロゲンの減少を補う作用が期待できる大豆イソフラボンには、骨密度の低下を防ぎ骨粗しょう症の予防や改善が望めるといえます。
2-2.更年期障害の軽減
大豆イソフラボンには、更年期障害を軽減する効果が期待できるといわれています。
更年期障害は火照りやのぼせ、目まいや動悸(どうき)などの身体症状や、気分の落ち込みやイライラなどの精神症状といったさまざまな表れ方をします。
女性の更年期障害の主な原因は、女性ホルモンであるエストロゲンが減少することだといわれています。
それに加えて加齢などの身体的要因や性格などの心理的要因、職場や家庭における人間関係などの社会的要因などが複合的に関与して発症すると考えられています。
大豆イソフラボンには、エストロゲンが減少したときに代わりとなってエストロゲンに似たようなはたらきがあるといわれています。
そのため、エストロゲンの分泌量の低下によって起こる更年期障害を軽減する効果が期待できると考えられるでしょう。
3.大豆イソフラボンを過剰に摂取した場合の影響
「大豆イソフラボンはたくさん摂った方が効果は期待できるのかな?」
「大豆イソフラボンの摂り過ぎによる悪影響があるのか気になる……」
体にとって良い効果が期待できる一方、摂り過ぎた場合にどんな影響があるのかも気になりますよね。
通常の食事に含まれている大豆イソフラボンを摂取する場合は問題ないとされています。
しかし、サプリメントなどから大豆イソフラボンを過剰に摂取した場合には乳がんの発症や再発のリスクを高めたり、妊娠中の場合は胎児の発育に影響が出たりする恐れがあるという報告もあります。
そのため、特に妊娠中は自己判断でのサプリメントなどの摂取は避ける必要があります。
また、長期間にわたり閉経後の女性が大豆イソフラボンを多量に摂取することで「子宮内膜症」の発症を高めるとされています。
ただし、ヒトに対する大豆イソフラボンの安全性についてはまだ研究の途上にあるといわれるため、過剰に心配をし過ぎる必要はないともいえるかもしれません。
4.大豆イソフラボンの摂取目安量
「大豆イソフラボンはどの程度まで摂取して良いのかな?」
という点が気になっている方もいらっしゃるでしょう。
大豆イソフラボンの1日当たりの摂取目安量の上限値は、大豆イソフラボンアグリコンとして70~75mgとされています[1]。
ただし、これは毎日欠かさずに長期的に摂取した場合の値であり、この上限値を超えることによって直ちに健康被害につながるというわけではありません。
また、通常の食品からの摂取に加え特定保健用食品として大豆イソフラボンを摂取する場合は、通常の上限値に加え1日当たり30mgを目安としています[1]。
この値は大豆イソフラボンアグリコンとしての換算量です。
念のため、以上の数値を参考にして大豆イソフラボンを摂り過ぎないよう注意する必要があります。
心配な場合はサプリメントの種類や摂取量などをかかりつけ医に相談するようにしましょう。
5.大豆イソフラボンを含む食品
「大豆イソフラボンはどんな食品に含まれているんだろう?」
というポイントが一番気になるところですよね。
原料大豆の種類や食品の製造方法などによって含有量は異なりますが、大豆イソフラボンは大豆を原料とする食品のほとんどに含まれています。
大豆食品100g当たりの大豆イソフラボンアグリコン含有量を食品別にご紹介します。
【大豆食品100g当たりの大豆イソフラボンアグリコン含有量】
| 食品名(検体数) | 含有量 | 平均含有量 |
|---|---|---|
| きな粉(2検体) | 211.1~321.4mg | 266.2mg |
| 揚げ大豆(1検体) | 200.7mg | 200.7mg |
| 大豆(11検体) | 88.3~207.7mg | 140.4mg |
| 凍り豆腐(1検体) | 88.5mg | 88.5mg |
| 納豆(2検体) | 65.6~81.3mg | 73.5mg |
| 煮大豆(3検体) | 69.0~74.7mg | 72.1mg |
| みそ(8検体) | 12.8~81.4mg | 49.7mg |
| 油揚げ類(3検体) | 28.8~53.4mg | 39.2mg |
| 豆乳(3検体) | 7.6~59.4mg | 24.8mg |
| 豆腐(4検体) | 17.1~24.3mg | 20.3mg |
豆腐や納豆、煮大豆など日本の伝統食として親しまれている食品には、大豆イソフラボンが含まれているといえますね。
6.大豆イソフラボンについてのまとめ
植物性エストロゲンとも呼ばれる大豆イソフラボンには、骨粗しょう症の予防や改善、更年期障害の軽減などの作用がある可能性があるといわれています。
骨折を招きやすくなる骨粗しょう症や、目まいや火照り、動悸、情緒不安定といったさまざまな症状を心身にもたらす更年期障害に効果が期待できるのはうれしいですよね。
日々の食生活で大豆食品が足りていないと感じる方は、ぜひ食卓に取り入れてみてくださいね。
しかし、過剰に摂取した場合は子宮内膜症や乳がんの発症を高める可能性も示唆されており、特に妊娠中は胎児への影響を考慮し、摂取量に気を付ける必要があります。
ただ、大豆イソフラボンによる悪影響を心配して大豆食品を食べることをやめてしまうと、大豆食品からの栄養成分が得られなくなり、かえって健康を損なう可能性もあります。
一方で、大豆イソフラボンについてはまだ研究が進められている段階で効果や安全性については全てが明らかになっているわけではないので、念のため注意しておきましょう。