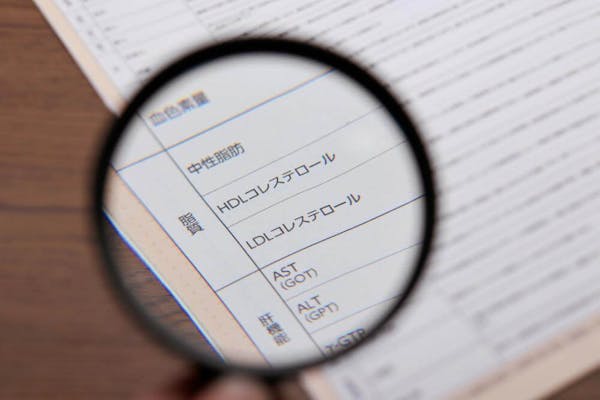中性脂肪が高いと言われたらチェックすべき7つのこと
「職場の健康診断で中性脂肪の数値が高いって言われちゃった」
「中性脂肪ってなんで増えるの?増えたらどうなるの?」
このように、健康診断で中性脂肪が高い数値だったり、ご自身で気になったりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
中性脂肪は、人が健康的に生きていくためにある程度の量は必要です。
ただし、多過ぎる(値が高過ぎる)と、生活習慣病のリスクにつながります。
この記事では、「中性脂肪とは何だろう?高いとどのようなリスクがあるんだろう?」
という疑問への回答とともに、日常生活で注意したい七つのチェックポイントを紹介します。
1.中性脂肪とは?どんな役割をもつ?
中性脂肪は、動物や植物に含まれる脂質のことです。
グリセロールという物質で3本の脂肪酸を束ねた構造となっており、体を構成する細胞を作るために必要な成分の一つです。
人間の体脂肪の大部分を占める物質でもあり、単純に脂肪と呼ばれることもあります。
エネルギー源の一種にあたる中性脂肪は、人間や動物にとって脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の摂取にも欠かせない成分です。
ただし、摂り過ぎると体脂肪として蓄積されてしまうため、バランスの良い食事で適切に摂取することが大切です。
中性脂肪は、別名トリアシルグリセロールやトリグリセリドとも呼ばれています。
健康診断で測定する中性脂肪は、血中のトリアシルグリセロール濃度を示した数値です。
普段の食事で摂取している油脂成分の多くを、トリアシルグリセロールが占めています。
2.中性脂肪が高い場合のリスク
健康診断で中性脂肪が高いと言われたら、血中のトリアシルグリセロール濃度が高く、摂取し過ぎている状態です。
摂り過ぎた中性脂肪が蓄積されて肥満になると、生活習慣病のリスクが高くなります。
中性脂肪が高かった場合は、特に以下の生活習慣病に注意しましょう。
2-1.脂質異常症とは?原因とされる物質について
血液中の脂質が基準値よりも多過ぎたり少な過ぎたりする状態のことを、脂質異常症と呼びます。
脂質異常症を招く物質は複数あり、例えば悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や善玉コレステロール(HDLコレステロール)、中性脂肪などです。
原因とされる物質ごとに、厳密には下記のとおり名称が異なります。
| LDLコレステロールが多過ぎる場合 | 高LDLコレステロール血症 |
| HDLコレステロールが少な過ぎる場合 | 低HDLコレステロール血症 |
| 中性脂肪が多過ぎる場合 | 高トリグリセリド血症 |
過去に総コレステロールやLDLコレステロール、中性脂肪のいずれかが高過ぎる人、もしくはHDLコレステロールが低い人は、「高脂血症」としてひとまとめに診断されていました。
そのなかで、総コレステロールが高い人で、LDLコレステロールは正常値である一方、HDLコレステロールが低い場合も「高脂血症」に含まれていました。
しかし、高脂血症はコレステロール値が高い状態を指す言葉であり、診断名として不適切であったため、現在は上記のとおり、総じて脂質異常症と呼ばれるようになりました。
脂質異常症を放置すると、動脈硬化ひいては脳梗塞や心筋梗塞などの原因となることもあります。
2-2.動脈硬化症とは?どんな状態?
動脈硬化症は、動脈が硬くなって弾力性を失った状態です。
血管の内側に、プラークと呼ばれるLDLコレステロール由来の物質や、カルシウムが付着することで、血管が硬くなります。
動脈硬化症によって引き起こされる代表的な病気は、心筋梗塞や脳梗塞などです。
症状は動脈硬化症が起こる部位によって異なります。
とはいえ、血管が細くなったり血栓ができて詰まったりすることで、血液がスムーズに流れなくなって引き起こされる点は同じです。
動脈硬化症は、多くの血液が流れる太い血管のみで起こるわけではありません。
脳や腎臓に広がる細い血管で生じることもあり、場合によっては血管が破裂する原因にもなり得るのです。
動脈硬化を招きやすいとされる危険因子として、コレステロールのほかに肥満や高血圧、喫煙や運動不足など複数あげられます。
2-3.糖尿病とは?どんなリスクにつながる?
血液中のブドウ糖濃度が多くなり過ぎると、糖尿病になります。
初期症状はほとんどないため気付きにくく、そのまま進行すると脳梗塞や脳出血を含む脳卒中や狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクにつながるのが特徴です。
動脈硬化症の危険因子である脂質異常症に糖尿病などの他の危険因子が重なると、それぞれの程度が低くても動脈硬化が進行することが分かっています。
そのため中性脂肪が高い方は、糖尿病にも注意しましょう。
また、糖尿病とともに注意したいのが、網膜症、腎症、神経障害の三大合併症です。
ブドウ糖は、筋肉や脳を動かすエネルギー源となります。
ブドウ糖が細胞に入るためには、すい臓から分泌されるインスリンが欠かせません。
糖尿病はインスリンの分泌量が減ったり効かなくなったりした状態であり、細胞に入れなくなったブドウ糖が血液中に残ってしまいます。
糖尿病は前述の三大合併症のほかにも脳卒中や認知症など、さまざまなリスクにつながるため、定期的な健診で初期のうちに気付くことが大切です。
2-4.高血圧症とは?原因はさまざま
血圧が正常値よりも高い傾向にあるのが、高血圧症です。
検診や病院で測定した際に収縮期血圧(最高血圧)が140mmHg以上、あるいは拡張期血圧(最低血圧)が90mmHg以上となった場合、高血圧症と判断されます。
ただし血圧は変動を繰り返しており、不安や緊張、ストレス、興奮などにより血圧が一時的に高くなるケースもあります。
血圧が高くなる原因は、さまざまです。
塩分の摂り過ぎや肥満、飲酒、運動不足などが原因と考えられます。
日本人にとって、喫煙と高血圧は生活習慣病の代表的なリスク要因です。
なお、高血圧症も動脈硬化症の危険因子の一つです。
そのため危険因子が重なるのを防ぐために中性脂肪が高い方は、高血圧症にも気を付けることをおすすめします。
3.中性脂肪の数値は30~149mg/dLを目指そう
生活習慣を見直すとともに、中性脂肪がどの程度高いか、検査表の数値で具体的に理解することが大切です。
また、中性脂肪と同じく脂質異常症などさまざまな症状の要因となるHDLコレステロールやLDLコレステロールの数値も、あわせて確認しましょう。
中性脂肪やHDLコレステロール、LDLコレステロールの数値の目安は、下記のとおりです[1]。
| 異常 | 要注意 | 基準範囲 | |
|---|---|---|---|
| LDLコレステロール (LDL-C) |
59以下 180以上 |
120~179 | 60~119 |
| HDLコレステロール (HDL-C) |
34以下 | 35~39 | 40以上 |
| 中性脂肪 トリグリセリド(TG) |
29以下 500以上 |
150~499 | 30~149 |
※(単位 mg/dL)
脂質やコレステロールの管理は、上記のとおりHDLコレステロールは40mg/dL以上、LDLコレステロールは60~119mg/dL、中性脂肪は30~149 mg/dLが基準範囲です。
4.中性脂肪が高いと言われたらチェックすべき7つのこと
中性脂肪が高いと言われたら、普段の生活を見直すチャンスです。
以下にあげる七つのチェックポイントで、当てはまるものがないか探してみましょう。
当てはまるものが一つでもある場合は、改善することが大切です。
4-1.✓摂取カロリーを摂り過ぎていないか
中性脂肪が高いと言われたら、肥満状態となっている場合や、摂取カロリーが多過ぎる可能性があげられます。
標準体重を維持するように心掛け、普段の食事で摂取カロリーを管理しましょう。
無意識のうちに、高カロリー食を選んでいないでしょうか。
摂取エネルギーが過剰になると、肝臓によるコレステロールの合成も進みます。
脂質のほか、糖質などの過剰摂取にも注意すべきです。
4-2.✓肉中心の食生活になっていないか
肉中心の食生活となっている方は、飽和脂肪酸による作用で血中の中性脂肪やコレステロールが増えやすい傾向にあります。
肉には飽和脂肪酸が含まれているため、高頻度で肉料理をメインにしている方は、食生活を見直してみましょう。
例えば、魚料理を中心にする方法があげられます。
アジやサンマなどの青魚にはDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸が多く含まれており、中性脂肪やコレステロールを減らすはたらきがあります。
4-3.✓脂質を摂り過ぎていないか
脂質を摂り過ぎている場合、中性脂肪やLDLコレステロールの増加につながります。
脂質は調味料にも含まれており、食生活に注意していても意図せず摂取してしまうことも少なくありません。
特に注意すべき調味料は、バターやマヨネーズなどがあげられます。
食材や調理済みのものでは、魚卵やレバーなどコレステロールが多く含まれているもの、天ぷらやフライなどの揚げ物に注意しましょう。
4-4.✓食物繊維不足になっていないか
日頃の食事で、食物繊維を十分に摂取できていないと感じる方も多いのではないでしょうか。
食物繊維には、血中コレステロールを低下させる作用があります。
そのほか、血糖値の上昇を抑えたり、整腸作用を促進させたりするなど、健康面での改善が期待できます。
欧米で行われた研究では、1日当たり24gの食物繊維を摂取すると心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクが軽減したという例があります[2]。
日本人の摂取目標量は男性で21g以上、女性で18g以上とされています。(※ともに18歳~64歳の場合)
海藻、きのこ、こんにゃくなど、食物繊維が豊富な食品を積極的に毎日のメニューへ加えましょう。
4-5.✓お酒を飲み過ぎていないか
アルコールは、適度な量であれば血管を広げたり、HDLコレステロールを増やしたりする作用が期待できます。
しかし飲み過ぎると、中性脂肪を増加させるほか、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の原因となるため、注意が必要です。
一般的に、各種酒類の適量とされている目安は、下記のとおりです[3]。
| 酒類 | 適量の目安 |
|---|---|
| ビール | 中びん1本(500ml) |
| 日本酒 | 1合(180ml) |
| 焼酎 | 0.5合(90ml) |
| ウイスキー | ダブル1杯(60ml) |
| ワイン | 2杯(240ml) |
目安を参考にしつつ、自分自身の体調や体質に合わせて、摂取量をコントロールすることが大切です。
頭痛や吐き気などが出やすい方、体質や年齢的に不安がある方は、目安量よりも控えめにしましょう。
4-6.✓運動不足になっていないか
一般的に、健康のためには適度な運動が必要であるといわれています。
健康診断などで中性脂肪の数値が高かったときは、運動不足になっていないか確認しましょう。
食事や間食による摂取エネルギーが消費エネルギーを超える状態になっていると、肥満になります。
余分な体脂肪の減少や肥満予防を目指すには、適度な運動で消費エネルギーを増やすことがポイントです。
厚生労働省によると、中強度以上の有酸素運動を1日30分以上、少なくとも週3日程度の頻度で続けることが推奨されています[4]。
中強度以上の有酸素運動とは、例えばウォーキング、水泳、スロージョギング、サイクリングなどです。
急に運動習慣を身につけるのは難しいと悩んでいる方は、一駅分歩いて帰るなど、普段より10分は多めに体を動かすことから始めてみてはいかがでしょうか[5]。
4-7.✓たばこを吸っていないか
たばこはLDLコレステロールを増やしたり、HDLコレステロールを減らしたりする作用があります。
血圧を高めるリスクもあり、動脈硬化を進行させる要因となるものです。
動脈が硬化すると虚血性心疾患や脳卒中のリスクが高まるため、喫煙習慣がある方は注意しましょう。
すでにたばこを吸う習慣がある方は、禁煙すると前述のような病気リスクを軽減できます。
禁煙は医師への相談をおすすめします。
普段たばこを吸わない方は、受動喫煙を回避することも効果的です。
5.中性脂肪が高いと言われたら注意することについてのまとめ
健康診断で中性脂肪の数値が高かった場合は、食生活や運動習慣を見直してみましょう。
例えば、通勤を電車やバスから自転車に変えるなど、取り入れやすい対策から少しずつ実践していくことが大切です。
仕事の都合で外食が多い方は、注文するメニューを野菜やカロリーに注意して選んだり、食べ過ぎないように意識したりしましょう。
この記事の監修者
おだかクリニック
副院長
【経歴】
総合病院・大学病院での勤務を経て、2018年よりおだかクリニックの副院長として診療・経営にあたる。専門の循環器疾患(虚血性心疾患、心不全、不整脈など)はもちろんのこと、高血圧や高脂血症、糖尿病等の生活習慣病や内科疾患全般の診療に従事。現在は、医療コンサルト・アドバイザー業務や、ライティング業務などにもあたっている。
【おだかクリニックのHP情報】
»医療法人日和会 おだかクリニック