「最近、ちょっと動いただけでめまいがする」
「めまいの原因って何?もしかして高血圧ぎみなのかも?」
このように、めまいがあると高血圧と関係しているのではないか?と気にする方は多いのではないでしょうか。実は、必ずしもめまいが高血圧の症状であるとは限りません。
しかし、なんらかの原因で高血圧とともに、めまいが生じてしまう病気や症状があります。
この記事では、めまいと高血圧で考えられる病気や症状、高血圧のリスクが高いと思ったときにすべき予防策について解説します。
1.めまいは高血圧の症状?
天井や景色がグルグルと回って見えたり、普通に立っているつもりがふらふらと平衡を保てなくなったりすることを、めまいと呼びます。
めまいが起こると起き上がって生活するのも大変なことがあり、「もしかして何か重大な病気にかかっているのかもしれない」と不安になるものです。なかには生活習慣や年齢を理由に、高血圧との関連性を心配する方もいるのではないでしょうか。
【関連情報】 「高血圧とは?基準値や健康上のリスク、改善のポイントを徹底解説」についての記事はこちら
1-1.高血圧は基本的に無症状である
高血圧とは、血圧が基準値よりも高い状態を指します。さまざまな病気のリスクを高めるとされる一方、高血圧自体は基本的に無症状であるのが特徴です。
日本高血圧学会によると、日本国内の高血圧者数は約4,300万人と推定されています。うち約3分の1にあたる1,400万人は、自分が高血圧であることを認識していないとされています[1]。
1-2.めまいは高血圧の一般的な症状ではない
高血圧そのものには自覚症状がない一方で、二次性高血圧、高血圧合併症、臓器障害にともなう特異的症状などにより、なんらかの症状が現れるケースはあります。
例えば以下のような自覚症状は、高血圧に関連する可能性が考えられます。
- 夜間頻尿
- 夜間呼吸困難
- 早朝の頭痛
- 昼間の眠気
- 集中力の低下
- 抑うつ状態 など
上記は、ホルモン異常や薬剤などで誘発される二次性高血圧にともなって起こる可能性がある症状です。漢方薬や免疫抑制薬など血圧を高める薬剤の使用状況、臓器障害の有無などが関係することがあります。
高血圧を主な原因とするめまいは、一般的ではありません。めまいが含まれる病気や症状は、自律神経失調症や突発性難聴、更年期障害、うつ病、不眠症などがあげられます。
2.めまいと高血圧で考えられる病気・症状
高血圧がめまいに直結することは多くありません。ただし、なんらかの原因で高血圧とともにめまいが生じるケースもあります。
めまいと高血圧の両方が生じている場合、可能性としてあげられる病気や症状は、次の六つです。
2-1.脳血管障害
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの症状は、総じて脳血管障害と呼ばれます。脳血管障害は、高血圧と合併しやすいのが特徴です。
高血圧と脳血管障害を併発すると一過性脳虚血発作(脳梗塞様の症状が一過性に出現し24時間以内に改善する)、筋力低下、頭痛、視力障害などの症状がみられることもあれば、めまいが生じる場合もあります。
日本の場合、脳血管障害の中でも特に脳梗塞患者が多いとされています。症状が現れる急性期に高血圧を合併しているケースが多く、いかに血圧管理を行うかが重要です。
2-2.降圧薬による脳虚血性徴候/脳循環不全症状
高血圧の治療には、生活習慣の改善のほかに薬物療法が用いられることもあります。血圧を下げる降圧薬が使用された結果、生じることがあるのが脳虚血性徴候と呼ばれる立ち眩み・めまいです。
降圧治療が行われる途中で、めまい、ふらつき、だるさ、頭重感、しびれなどの症状が現れた場合は、血圧を下げたことによる脳循環不全症状の可能性が考えられます。症状によっては、降圧薬の減量や変更などの対処が必要です。
年齢や血圧の高さ等によって異なりますが、一般的には、降圧薬は少量から様子を見つつ増量していきます。しかし前述の症状が顕著な場合は、増量する間隔を長く空けるなど各患者に合った判断が行われます。
2-3.降圧薬による副作用
使用する降圧薬の影響で、めまいが現れることもあります。例えば中枢性交感神経抑制薬の一種、カタプレス(クロニジン塩酸塩)またはワイテンス(グアナベンズ酢酸塩)を使用した場合の副作用です。
中枢性交感神経抑制薬は、RA系阻害薬やCa 拮抗薬、サイアザイド系利尿薬などほかの降圧薬を使用したときに目標の数値へ到達しない場合、追加される薬剤です。カタプレスやワイテンスは、眠気や口渇に加えて、めまいも副作用として報告されています。
1種類の降圧薬では効果が不足する場合でも、複数の降圧薬を組み合わせることでコントロール可能になるケースが多いです。高血圧の原因や、患者にとって必要と判断した場合、副作用も考慮した上で中枢性交感神経抑制薬が併用されることもあります。
2-4.起立性低血圧
低血圧が高血圧やめまいの症状につながるケースもあります。起立性低血圧(急に立ち上がったときに血圧が下がること)などの症状が現れる起立性血圧変動異常者は、同時に仮面高血圧が起こりやすい特徴をもっています。
仮面高血圧とは、診察時は正常であるのに、普段は血圧が高い状態のことです。起立性低血圧は仮面高血圧のほかにも、めまいや動悸、失神の症状が見られることがあります。
また、抗うつ薬やパーキンソン治療薬など、血圧を上げる作用がありつつも起立性低血圧を引き起こしやすい薬剤もあります。
2-5.高安動脈炎
比較的まれな疾患として、高安動脈炎もあげられます。大動脈などの太い血管に慢性的な炎症が起こる、自己免疫疾患の一種です。日本国内においては女性の発症率が高い傾向にあります。
初診時に患者が訴える症状の中には、失神や視力障害、発熱などとともに、高血圧、めまいも含まれます。かつて大動脈炎症候群と呼ばれていましたが、大動脈以外の場所にも異常が現れることから、近年は高安動脈炎の呼び名が一般化しました。
さまざまな異常が見られる一方で、高安動脈炎には特徴的な症状がないため、長期間、診断がつかないこともあります。
2-6.パニック障害/過換気症候群
パニック障害や過換気症候群は、頻脈、動悸、呼吸困難、めまいなどの症状が起こるのが特徴です。いずれの症状も、発作性血圧上昇につながるため、一時的な高血圧が生じます。
もともと血圧は、変動しやすいものです。前述の仮面高血圧のように、条件が普段と異なるだけで数値が大きく変わることも多く、精神的要因によっても変動します。
怒りや不安の感情にかられたときに一過性の症状として現れる場合もあり、パニック障害や過換気症候群にともなって血圧が上がるのも、自然な反応です。
正常な血圧が一過性の高血圧となるケースのほか、高血圧の傾向にある方が発作的にさらに血圧上昇する場合もあります。パニック障害に関連する高血圧が、心筋梗塞や脳卒中などのリスクとなることも報告されています。
3.このままだと危険かも……高血圧のチェックリスト!
複数の症状をあげたとおり、高血圧はさまざまな要因で起こります。ときには症状の一部としてめまい・高血圧が生じることもある一方で、多少血圧が高い程度の場合は、無症状であることも多いのが特徴です。
しかし、無症状だからといって放置していると、脳卒中や心疾患リスクを高めかねません。慢性腎臓病や血管性認知症など、ほかにも多くのリスクにつながります。
高血圧を見逃さないためには、普段から自身の体調管理を意識し、生活習慣を見直すことが大切です。
まずは以下のチェックリストにて、自身が高血圧である可能性を確認してみましょう。
日頃から自分の血圧を確認したい方は、家庭血圧(自宅で毎日はかる血圧の数値)で、血圧管理を始めることをおすすめします。家庭血圧を記録するときは、毎日決まった時間に測ることがポイントです。
3-1.塩分の多い食品・料理をよく食べる
塩分の摂り過ぎは、高血圧のリスクを高める恐れがあるため、食事内容には注意しましょう。現代人の食生活は、塩分の多いメニューがあふれており、知らないうちに過剰摂取している可能性があります。
塩分を摂り過ぎると、体が血液の浸透圧を一定に保つよう血液中の水分を増やします。その結果、血管の壁にかかる圧力が増えてしまい、血圧が上がりやすくなるのです。
日本人が日常的に口にする食品や料理のうち、塩分が多いとされるものは、下記のとおりです。
- かけうどん・かけそば
- カップめん
- 漬物(梅干し・たくあんなど)
- ハムや干物などの加工食品
- 醤油やみそなどの調味料
塩分は調味料のほかにも、ハムや干物などの加工食品や漬物、練り製品などにも多く含まれています。
普段は濃い味付けのものを好んで食べてしまう、料理に調味料を多めに入れてしまうという方は、塩分の量を意識して減らしましょう。
3-2.食べ過ぎで肥満になっている
おいしいものを食べるのがストレス解消や趣味になっている方は、多いのではないでしょうか。しかし食べ過ぎて肥満になると、高血圧につながります。
肥満になると、インスリンのはたらきが悪くなるためです。インスリンはすい臓から分泌されるホルモンであり、血中のブドウ糖をエネルギー源として細胞に行きわたらせ、血糖値を一定の状態に保つはたらきをもちます。はたらきが悪くなると過剰に分泌されるようになり、交感神経を刺激して血圧を上昇させる恐れがあります。
近年は、肥満が原因と考えられる高血圧者が増加している傾向にあります。高血圧に関連するさまざまな病気リスクを予防するためにも、肥満を避け、食事や間食は適度な量に抑えることが大切です。
3-3.運動不足である
運動不足は、高血圧における環境要因の一つです。運動不足による身体活動量の低下は、脳心血管病発症リスクを高めるともいわれています。
高血圧の傾向が見られる患者に対して、生活習慣改善の一つに運動療法が加えられることが多いのも、脳心血管病発症リスクとの関連性があるためです。
運動不足の解消は、高血圧予防や持久力増加など健康増進に役立ちます。高血圧のみならず、さまざまな病気リスクを軽減するためにも、運動不足になっていないか生活習慣を見直してみましょう。
3-4.喫煙している
たばこに含まれるニコチンは交感神経を刺激するため、血圧の上昇につながります。また、たばこを吸うと一酸化炭素が体内に取り込まれ、血液中の酸素が不足してしまい、心臓に負担がかかってしまうのです。
紙巻たばこを1本吸うと、血圧上昇が15分程度続くとされています。1日15本以上喫煙する方は、高血圧の発症割合が高いとの報告もあるため注意が必要です[2]。少ない本数であっても、体への悪影響は変わりません。
喫煙習慣がない方であっても、受動喫煙によって高血圧有病率が高まるリスクが海外の研究で示されています。「自分自身は喫煙しないが、同居の家族や身内が日常的に吸っている」という方も、たばこの煙による影響が考えられます。
3-5.お酒をよく飲む
仕事終わりは同僚とよく飲みに行く方や、休日前は眠くなるまでお酒を飲んでいるという方は、飲み過ぎることが日常になっていないでしょうか。お酒の飲み過ぎは血圧の上昇に加え、カロリー過多による肥満を招く恐れがあります。
お酒は過剰摂取を避け、適量を楽しく飲むことが大切です。厚生労働省では、1日に摂取するアルコールの適量は約20gを目安としています。各アルコール飲料の含有量は、ビール(500ml)やウイスキー(60ml)で20g、清酒(180ml)で22g程度です[3]。
上記を超える飲酒量となっている場合は、高血圧のリスクが高くなります。
3-6.ストレスが溜まっている
精神的または身体的なストレスを抱えることも、高血圧につながる可能性があります。ストレスが交感神経を刺激して自律神経の乱れを起こし、血圧を上昇させるためです。
血圧は、交感神経と副交感神経の働きによってコントロールされています。ストレスで自律神経が乱れて、交感神経と副交感神経のバランスが崩れれば、血圧も調整しにくくなります。
3-7.睡眠不足が続いている
自律神経の乱れにつながる要素の一つが、睡眠不足です。十分な睡眠を取れていない状態は、身体的なストレスが溜まっているともいえます。
副交感神経のはたらきによって、睡眠時は血圧が低くなるのが通常です。睡眠不足になると、交感神経の影響で血圧が高い状態が続き、心筋梗塞や脳卒中などのリスクを高めます。
また、不規則な生活も高血圧になる原因です。日によってはたっぷり眠れているという方も、不規則な生活で自律神経が乱れている可能性があります。
4.高血圧のリスクが高いと思ったときにできること
前述のチェック項目に当てはまる部分があった方は、少しずつ生活習慣の改善を行い、高血圧リスクを軽減させましょう。
高血圧のリスクが高いと感じた方が、まず取り組めることとして、次の三つがあげられます。
4-1.食生活を見直す
前述のとおり、食塩の過剰摂取や肥満など、食生活の乱れと高血圧は深い関係があります。血圧が気になる方は、第一歩として食生活の見直しを行うことが大切です。
基本的な食事のポイントは、以下の四つです。
【食生活を見直すときのポイント】
- 減塩する(1日6g未満が目安)
- 野菜・果物を意識して取り入れる
- 体重のコントロールを行う
- 節酒する
食塩は知らず知らずのうちに過剰摂取してしまうことがあるため、高血圧の傾向がある方は1日6g未満まで減らすように意識しましょう。食塩のみならず、食品に表示されている「食塩相当量」も考慮することが大切です[4]。
減塩に役立つのが、野菜や果物です。過剰に摂取した塩分を体外へ排出してくれるカリウムを豊富に含んでいるため、毎日の食事に意識して野菜や果物を取り入れてみましょう。野菜は1皿以上、果物はバナナやオレンジで1本(個)程度から始めると、無理なく摂取できます。
肥満やアルコールによる高血圧を避けるためにも、食事は腹八分目、アルコールは前述の適量(20g)を目安にすることもポイントです。
4-2.運動を習慣化する
さまざまな病気リスクの軽減など、健康増進の方法として注目されているのが、運動不足の解消です。環境的に本格的な筋トレが難しい方も、手軽な運動から取り入れていきましょう。高血圧予防を目的とするなら、有酸素運動が効果的です。
有酸素運動を習慣化すると、収縮期血圧で2-5mmHg、拡張期血圧で1-4mmHg程度の血圧低下が期待できます[5]。
最初から、無理に負荷の大きな運動をする必要はありません。「ややきつい」と感じる程度の運動強度で、毎日30分以上続けることが理想です。メニューを作るときは、スクワットや腕立て伏せなど筋肉に抵抗をかけるレジスタンス運動と、ストレッチ運動を組み合わせましょう。
高血圧の人におすすめの運動メニューを知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。
4-3.禁煙する
高血圧予防として、非常に重要なのが禁煙です。日頃から喫煙の習慣がある方はもちろん、職場や家庭などで日常的に受動喫煙の状態となっている方も、たばこの煙を意識して避けることが大切です。
喫煙習慣があり、禁煙が難しい方は、保険診療で専門的な指導を受ける方法もあります。また、禁煙補助薬も複数発売されているので、自分に合った方法を探してみましょう。
5.高血圧は早期発見・早期治療が大切!
前述のとおり、高血圧は基本的に自覚症状がないのが特徴です。なんらかの症状が現れる急性期は合併症を発している場合があるなど、進行している可能性があります。
最初は自覚症状がないからこそ、まずは意識的に自分が高血圧なのかどうかを判断する機会を設けることが大切です。健康診断の結果を細かく確認したり、生活習慣を見直したりと、普段から健康状態を意識する習慣をつけましょう。
健康寿命を延ばすためにも、さまざまな病気のリスクにつながる高血圧の早期発見・早期治療が大切です。高血圧と診断された場合は、継続的な治療によって降圧目標を達成していくように努めましょう。
6.高血圧に関する症状とめまいについてのまとめ
高血圧に関連する症状は、複数あげられます。ただし、高血圧そのものは無症状である場合が多いため、なんらかの違和感があるときはほかの病気を疑うことも大切です。
めまいが起こると、「高血圧かもしれない」と不安になりますが、必ずしも血圧が原因とは限りません。睡眠不足やストレス、食習慣などによってめまいを起こす場合もあるため、まずは日々の生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
また、高血圧をはじめ無症状のまま進行する病気・症状は少なくありません。定期的に健康診断を受け、早期発見などで病気のリスクを軽減できるように意識しましょう。
この記事の監修者
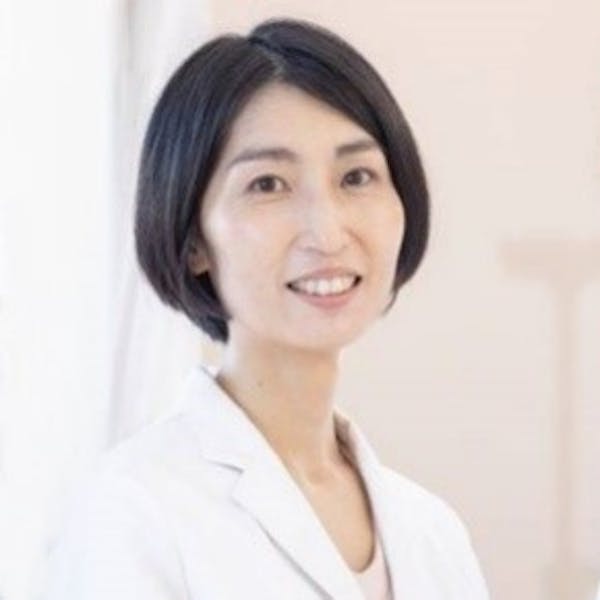
内科認定医・がん治療認定医
【経歴】
国立大学医学部医学科卒業後、公立病院にて初期研修の2年を終了後、3年目からはがん治療を専門としながら幅広く内科疾患の診療に従事。治療が必要となる前の生活習慣の改善、また病気についての正しい知識が大事であることを実感し、病気についての執筆活動にもあたっている。






































