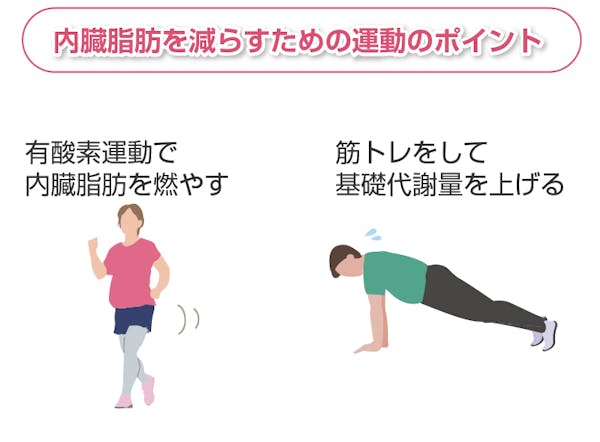ぽっこりお腹を改善するには?内臓脂肪を減らすためのポイント
「ぽっこりお腹(おなか)が気になる……」
「お腹周りの脂肪を減らすにはどうすれば良いんだろう?」
お腹周りに過剰に付いた脂肪がもたらす悪影響や、お腹の脂肪の減らし方が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ぽっこりお腹になるのは、「内臓脂肪」と呼ばれる脂肪が多く付いているせいだと考えられます。
内臓脂肪とは胃や腸などの内臓の周りに付く脂肪のことです。
内臓脂肪が過剰につくとおなかがぽっこりしてしまうだけでなく、「「メタボリックシンドローム」と呼ばれる状態に陥りやすくなり、重大な病気を引き起こすリスクも高くなります。
しかし、きちんとポイントを押さえておけば、内臓脂肪は減らすことができます。
この記事では、ぽっこりお腹になってしまう原因と内臓脂肪による悪影響を解説した後、内臓脂肪を減らすためのポイントを食事と運動という二つのカテゴリに分けて解説します。
1.ぽっこりお腹の原因は内臓脂肪
ぽっこりお腹になっている場合、内臓脂肪の蓄積が原因だと考えられます。
内臓脂肪とは胃や腸などの内臓の周りに付く脂肪のことです。
内臓脂肪が過剰に付いた状態を「内臓脂肪型肥満」といいます。
ウエスト周りに脂肪が付き、お腹がぽっこりした体形になるため「りんご型肥満」とも呼ばれます。
女性よりも男性の方に付きやすい傾向があるのも、内臓脂肪の特徴です。
また、内臓脂肪は皮下脂肪と比べて減らしやすいことが分かっています。
2.内臓脂肪による悪影響の代表は「動脈硬化」
「内臓脂肪が付いていると、体に良くないのかな?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
内臓脂肪が付き過ぎていると「動脈硬化」が進み、心筋梗塞や脳梗塞などといった命に関わる病気を発症しやすくなるとされています。
内臓脂肪型肥満や高血圧、高血糖、脂質異常症などは、単独でも動脈硬化の原因になるといわれていますが、これらが重なると動脈硬化が進行するリスクはさらに高まります。
また、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常症のうち二つ以上が同時に発症している状態を「メタボリックシンドローム」といいます。
つまりメタボリックシンドロームの状態では、動脈硬化が進行するリスクが高く、心筋梗塞や脳梗塞を発症しやすいといえます。
このためメタボリックシンドロームは予防・改善が必要だとされているのです。
3.内臓脂肪を減らすための食事のポイント
「ぽっこりお腹を引っ込めたいけど、どうして良いか分からない……」
このように悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。
内臓脂肪を減らしてぽっこりお腹を引っ込めるには、食生活と運動習慣の見直しが必要になります。
この章ではまず内臓脂肪を減らすための食事のポイントを解説します。
ポイント1 摂取カロリーを適切に制限する
どれくらいのカロリーを摂取すれば良いかは、目標とする体重での推定必要カロリー(推定エネルギー必要量)が目安になります。
ただし、目標体重はBMIを参照して決めると良いでしょう。
BMIは国際的に用いられている肥満度を表す指標で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出できます[1]。
なお、厚生労働省は年齢に応じて目標とするBMIの範囲を定めています。
| 年齢 | 目標とするBMI |
|---|---|
| 18〜49歳 | |
| 50〜64歳 | |
| 65歳以上 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
この範囲に収まるよう目標体重を決めましょう。
また、BMIをベースとして目標体重を計算する場合、[身長(m)の2乗]に目標とするBMIをかけることで求められます[1]。
消費カロリーは身体活動量によって変動するため、推定必要カロリーはどれだけ体を動かしているかによって異なります。
このため推定必要カロリーの計算には以下のとおり、身体活動レベルを用います。
| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、体を動かす機会があまりない場合 |
|---|---|
| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立った状態で作業・接客したりすることがある仕事に就いている場合、または通勤や買い物で歩いたり、家事をしたり、軽いスポーツを行ったりする習慣がある場合 |
| 高い | 移動したり立った状態で作業したりすることの多い仕事に就いている場合、または余暇にスポーツなどの活発な運動習慣がある場合 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
ご自身の年齢と身体活動レベルを下記の表と照らし合わせれば「体重1kg当たりの推定エネルギー必要量」が分かります。
その数値に、先に求めておいた標準体重をかければ摂取カロリーの目安が把握できます。
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |
| 18〜29歳 | ||||||
| 30〜49歳 | ||||||
| 50〜64歳 | ||||||
| 65〜74歳 | ||||||
| 75歳以上 | ||||||
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
ご自身に合った摂取カロリーの目安を知り、食事から摂るカロリーができるだけその範囲内に収まるように工夫してみてくださいね。
ポイント2 糖質と脂質の摂取量を適切に制限する
内臓脂肪を減らすには糖質と脂質を適切に制限することが重要です。
体のエネルギー源となる、つまりカロリーがあるのは糖質(炭水化物)、脂質、たんぱく質の三つの「エネルギー産生栄養素」だけだということが分かっています。
糖質(炭水化物)とたんぱく質は1g当たり約4kcal、脂質は1g当たり約9kcalのエネルギーをつくり出します[2]。
たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、髪の毛など、ヒトの体をつくる材料になる他、ホルモンや酵素、抗体など、体の機能を調整する成分にもなる重要な栄養素です。
筋肉が減ってしまうと痩せにくい体になるので、摂取カロリーを減らしたいなら糖質(炭水化物)と脂質の摂取量を制限するのが良いといえるでしょう。
厚生労働省は1日に摂取するカロリーのうち、糖質(炭水化物)から摂取するカロリーを50〜65%、脂質から摂取するカロリーを20〜30%、たんぱく質から摂取するカロリーを18〜49歳までで13〜20%、50〜64歳で14〜20%、65歳以上なら15〜20%にするという目標量を定めています[2]。
糖質(炭水化物)はご飯、パン、麺類などの主食となる食べ物や、甘いお菓子・飲み物などの原材料に砂糖を使った食品に多く含まれます。
脂質は食用油やそれを原材料とするスナック菓子、マーガリンやバター、牛肉や豚肉に多く含まれています。
そのためご飯や麺類といった主食中心の食生活を改めるとともに、習慣的に摂取している甘いソフトドリンクやスイーツ、スナック菓子を控えたり、肉食中心の食生活を見直したりすると良いでしょう。
脂質の場合、炒める、揚げるといった油を使う調理法を、煮る、蒸すといった油を使わない調理法に変えるだけでも摂取量を減らすことができます。
単に摂取するカロリーの総量を気にするだけではなく、摂取源となる栄養素にも気を配ることができるとさらに良いのですね。
ポイント3 食物繊維を十分に摂る
十分な量の「食物繊維」を摂ることも、内臓脂肪を減らしてぽっこりお腹対策を行うことにつながります。
加えて食物繊維にはお腹の調子を整え、脂質や糖質、ナトリウムを体外に排出するはたらきがあるため、内臓脂肪の減少が期待できます。
1g当たり0〜2kcalと低カロリーなことも、うれしいポイントです[3]。
しかし、厚生労働省によると日本人の食物繊維摂取量は減少傾向にあり、最近の20歳以上の平均摂取量は1日当たり約18gとされています[4]。
また、厚生労働省の定める1日当たりの食物繊維摂取目標量は以下のとおりです。
<class="midpush">【1日当たりの食物繊維の目標量】
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | ||
| 30~49歳 | ||
| 50~64歳 | ||
| 65~74歳 | ||
| 75歳以上 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
不足しがちな栄養素なので、少しでも食物繊維の摂取量を増やすことを心掛けましょう。
食物繊維は野菜類、海藻類、きのこ類、豆類などに多く含まれます。
具体的にはさつまいもやかぼちゃ、ごぼう、たけのこ、納豆、いんげん豆、おから、しいたけ、ひじきなどには食物繊維が多く含まれていることが分かっています。
また、主食類ではそばやライ麦パンなどに多く含まれます。
これらの食品には、1食当たりの摂取量に食物繊維が2〜3gも含まれています[5]。
そのため効率的に食物繊維を摂りたい方には、これらの食品からの摂取をおすすめします。
さらに1日のうち1食を、白いご飯から玄米ご飯、麦ご飯、胚芽米ご飯などに置き換えることでも、食物繊維の摂取量は増やすことができます。
ポイント4 規則正しく食事を摂る
内臓脂肪を減らしてぽっこりお腹を少なくするには、規則正しく食事を摂ることも重要です。
食後すぐに甘いものを食べたり、食事と食事の間が開き、お腹がすいて1度に食べる量が増えたりすると、血糖値が上昇しやすくなります。
血糖値が急上昇すると「インスリン」が過剰に分泌されます。
インスリンには使い切れなかった糖を体脂肪として蓄えるはたらきを促進する性質があるため、不規則な生活は内臓脂肪の増加につながります。
間食をなるべく控え、1回の食事量を適正に抑えるためにも、毎食の時間はきちんと決めておきましょう。
規則正しい食生活を送ることが、血糖値の急上昇を抑えることにつながります。
ポイント5 お酒をほどほどに控える
お酒の飲み過ぎは、ぽっこりお腹の原因となる内臓脂肪の増加につながります。
アルコールのカロリーは1g当たり約7kcalですが、体に蓄えられにくいとされています[6]。
しかし、アルコール飲料には糖質(炭水化物)やたんぱく質が含まれていることが多く、高カロリーなことがほとんどです。
さらにアルコールには食欲増進作用もあります。
お酒を飲むといつも以上に食が進んでしまうという方も多いのではないでしょうか。
お酒のつまみとなるものには脂質や糖質を多く含むものもあり、食べ過ぎはぽっこりお腹の原因になるといえるでしょう。
厚生労働省は適度な飲酒量を「純アルコール量」で1日平均約20gとしています[7]。
一般的なお酒における純アルコール20gに相当する量は以下のとおりです。
【純アルコール20g相当のお酒の種類と量】
| アルコール度数 | 量 | |
|---|---|---|
| ビール | 5% | 500mL(中瓶1本) |
| 缶チューハイ | 5% | 500mL(ロング缶1本) |
| ワイン | 14% | 180mL(1/4本) |
| 日本酒 | 15% | 180mL(1合) |
| 焼酎 | 25% | 110mL(0.6合) |
| ウイスキー | 43% | 60mL(ダブル1杯) |
公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成
また、アルコールの過剰摂取は生活習慣病のリスクを高めるとされているので、週に2日程度は休肝日を設けて節酒を意識することが推奨されています[9]。
[7] 厚生労働省「健康日本21」
4.内臓脂肪を減らすための運動のポイント
「運動をすると脂肪が減るのは分かるけど、具体的に何をすれば良いのかな?」
運動が脂肪の減少につながることはよく知られていますが、具体的に何をすれば良いのか分からない方もいらっしゃることでしょう。
この章では内臓脂肪を減らすための運動のポイントを解説します。
ポイント1 有酸素運動で内臓脂肪を燃やす
「有酸素運動」は脂肪をエネルギーとして利用するので、内臓脂肪の減少が期待できます。
運動だけで内臓脂肪を減らすには、少なくとも週当たり「10メッツ・時以上」の有酸素運動を行う必要があるとされています[11]。
下記の表に主な有酸素運動のメッツをまとめました。
【主な有酸素運動のメッツ】
| 有酸素運動 | メッツ |
|---|---|
| 散歩 | 3.5 |
| ジョギング | 7.0 |
| ランニング(時速8.0km) | 8.3 |
| 水中歩行(ゆっくり) | 2.5 |
| 水泳(自由形・ゆっくり) | 5.8 |
| エアロビクスダンス(低い強度) | 5.0 |
国立健康・栄養研究所「改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』」をもとに執筆者作成
例えばゆっくりとした水中歩行のメッツは「2.5」とされています。
週に4時間、ゆっくりとした水中歩行を行うと、「メッツ・時」は「2.5×4=10」となり、脂肪の燃焼が期待できます。
また、ジョギングやランニング、水泳など、より強度の高い運動を選べば、所要時間を短くすることが可能です。
自分に合った運動を見つけて、有酸素運動で週「10メッツ時・以上」を目指してみるのも良いですね。
[11]厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」
ポイント2 筋トレをして基礎代謝量を上げる
筋トレを行うと「基礎代謝量」が上がり、脂肪が付きにくい体をつくることができます。
筋肉量が多い人ほど基礎代謝量が高くなり、安静時のエネルギー消費量も多くなることが分かっています。
有酸素運動のように脂肪を直接エネルギーとして利用するわけではありませんが、脂肪を付きにくくするために筋トレを行うのも前向きな選択肢の一つです。
5.ぽっこりお腹についてのまとめ
ぽっこりお腹の原因は胃や腸の周りに付く内臓脂肪にあると考えられます。
内臓脂肪が付き過ぎていると動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる病気を引き起こすリスクが高まります。
過剰に蓄積した内臓脂肪は健康を損なうリスクを高めてしまうのです。
内臓脂肪を減らすには1日当たりの摂取カロリーを制限したり、脂質や糖質、アルコールの過剰摂取を控えたりすると良いとされています。
食物繊維を十分に摂ることや食事を規則正しく摂ることも重要です。
また、散歩やジョギングなどの有酸素運動には脂肪の燃焼作用が期待されるので、積極的に取り組むと良いでしょう。
筋肉量が増えると基礎代謝量が上がるので、脂肪が付きにくい体を目指したい方には筋トレもおすすめです。
健康的な生活を送るためにも、自分に合った方法で内臓脂肪を減らして、ぽっこりお腹を減らしていきましょう。