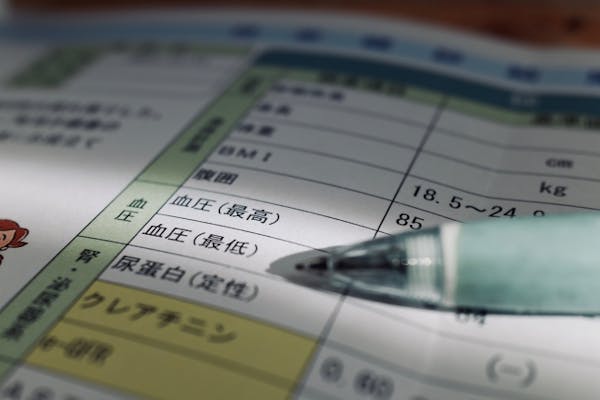「高血圧の原因って何だろう?」
「高血圧を改善するための方法が知りたい」
このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
高血圧には生活習慣や遺伝的要因によって起こるものと、他の病気や薬剤の影響により起こるものがあります。
日本人の高血圧の多くは生活習慣が原因で発症したものだといわれています。
この記事では高血圧の種類別での原因を詳しく解説します。
また高血圧を改善するためのポイントもご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
1.高血圧とは
高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態のことをいいます。
高血圧が長く続くと、重大な病気を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。
そもそも血圧とは、心臓から送り出された血液が「動脈」の内壁を押す力のことで、一般的には上腕にある動脈にかかる圧力のことを指します。
血圧には「最高血圧(収縮期血圧)」と「最低血圧(拡張期血圧)」があり、それぞれ「上の血圧」「下の血圧」と呼ばれることもあります。
最高血圧は心臓が収縮し血液を押し出したことによって血圧が最高に達したときの値で、最低血圧は心臓が広がって血圧が最低に達したときの値です。
血圧の基準値は病院で測定した診察室血圧と、家庭で測定した家庭血圧で異なります。
これは、診察室で測定する際には緊張で血圧が高くなることがあるためです。
高血圧の基準は診察室血圧で、最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上の場合です[1]。
一方家庭血圧では、最高血圧135mmHg以上または最低血圧85mmHg以上である場合に高血圧と診断されます[1]。
血圧は、心臓が血液を押し出す力、心臓から排出される血液量、血管の拡張度合いや弾力性などによって決まります。
このため、心臓から送り出される血液量が多かったり、送り出された血液が通る動脈が細く硬かったりするほど血圧は高くなるのです。
また血圧は測定する時間帯や季節、気温、食事、運動、精神的ストレスなど、さまざまな因子によっても変動します。
例えば運動後には一時的に血圧が上昇し、安静にすることで元に戻ります。
このように血圧は常に変動しているため、一度測定した血圧が高いだけでは高血圧といえません。
繰り返し測定しても、血圧が基準値より高い場合に高血圧と診断されるのです。
高血圧は自覚症状がないために気付かないうちに進行し、重大な病気を引き起こす危険性があることから「サイレントキラー」といわれることがあります。
高血圧が長く続くと「動脈硬化」が進行します。
高血圧による動脈硬化は太い血管にも細い血管にも起こり、生じた部位によって脳出血や脳梗塞、心筋梗塞、大動脈瘤、腎硬化症などさまざまな病気を引き起こす恐れがあります。
このため高血圧は症状の有無にかかわらず、放置せずに適切に治療を受けることが大切です。
高血圧は、明確な原因が分からない「本態性高血圧」と、なんらかの病気によって起こる「二次性高血圧」に分けられます。
次の章ではそれぞれの高血圧の原因について詳しく解説します。
動脈硬化や、引き起こされる病気、高血圧に関してはそれぞれ以下で詳しく解説しています。
動脈硬化とは?原因や病気のリスク、進行を防ぐポイントを徹底解説
[1] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」
2.本態性高血圧の原因
日本人の高血圧患者の約90%を占めるのが、本態性高血圧です[2]。
本態性高血圧は、生活習慣や遺伝的な要因が重なることにより発症するといわれています。
それでは、危険因子となる生活習慣や遺伝的な要因について見ていきましょう。
[2] 国立研究開発法人国立循環器病研究センター「高血圧」
2-1.塩分の過剰摂取
塩分の摂り過ぎは、本態性高血圧の原因です。
日本人の食生活では塩分が多くなりやすいため、高血圧の最大の危険因子とされています。
塩分は一般的に、食品に含まれる「食塩相当量」のことを指します。
食塩相当量は、食品に含まれる「ナトリウム」の量から換算された食塩(塩化ナトリウム)の量です。
塩分と血圧の関係はまだはっきりと分かっていませんが、食塩中のナトリウムが血圧上昇に関与しているとされています。
ヒトの体ではナトリウムや水分などの濃度が一定に保たれるよう調整されています。
塩分の摂り過ぎによって血中のナトリウム濃度が高まると、濃度を下げるために水分がため込まれます。
この結果体内を巡る血液量が増え、血管の壁にかかる力が大きくなることで血圧が上昇してしまうのです。
2-2.肥満
肥満も本態性高血圧の原因です。
肥満の人は食べ過ぎる傾向があり、それに伴って塩分も多く摂っていると考えられています。
また肥満では、血糖値を低下させる「インスリン」のはたらきが悪くなる「インスリン抵抗性」が起こります。
これにより血糖値が下がりにくくなると、膵臓からはより多くインスリンが分泌され血糖値を下げようとはたらきます。
インスリンは腎臓でのナトリウムの再吸収を促すため、分泌量が増えると血中のナトリウム濃度が上昇してしまいます。
こうして体内の血液量が増加し、血圧が高くなるのです。
加えて過剰に分泌されたインスリンの影響で「交感神経」が刺激されることも血圧を上昇させます。
交感神経が刺激されると、末梢血管を収縮させる「カテコールアミン」という神経伝達物質が分泌されるため、血圧が上昇するのです。
さらに、肥満で蓄積された脂肪細胞から「アンジオテンシノーゲン」という生理活性物質が分泌されることでも血管が収縮します。
肥満のさまざまな影響が、血圧上昇をもたらすのですね。
2-3.過度な飲酒
過度な飲酒も高血圧の原因です。
アルコールには血管を広げる作用があるため、少量であれば血圧を一時的に低下させるといわれています。
しかし、過度な飲酒や長期間の飲酒は血圧を上昇させる恐れがあります。
またアルコールは1g当たり7.1kcalと高カロリーであり[3]、それに加えて食欲増進作用を持ちます。
これにより肥満を招くことで高血圧になるのです。
この他、お酒のつまみとされるものには、塩分が多く含まれているものがあります。
塩分の多いおつまみを食べながら過度に飲酒する習慣には、肥満や高血圧を招く危険が多く潜んでいるのですね。
[3] 厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールのエネルギー(カロリー)」
2-4.運動不足
運動不足も本態性高血圧の原因です。
運動不足の状態では、血流が悪くなることがあります。
体の筋肉はポンプのようにはたらき、血の巡りをサポートしています。
しかし運動不足によって筋力が衰えると、血液を押し出す力が低下して血流が悪くなってしまいます。
心臓はより強い力で血液を送り出そうとはたらくため、血管の壁にかかる圧力が高くなるのです。
また運動不足は、高血圧の原因である肥満の要因にもなります。
これは、摂取したカロリー(エネルギー摂取量)を消費しきれず、体脂肪として蓄積するためです。
運動不足で血流が悪くなったり肥満を招いたりすることが高血圧のリスクになるのですね。
2-5.喫煙
喫煙も本態性高血圧の原因です。
たばこにはさまざまな有害物質が含まれています。
このうちニコチンや一酸化炭素は血圧を上昇させます。
ニコチンは交感神経を刺激し、血管を収縮させて血圧の上昇を招きます。
また一酸化炭素は体を酸素不足の状態に陥らせるため、結果として血圧上昇を引き起こします。
一酸化炭素は酸素に比べて200倍以上もヘモグロビンと結びつきやすい性質を持っています[4]。
このため喫煙で一酸化炭素が血液中に入ると、ヘモグロビンが酸素と結びつけなくなり、体が酸素不足の状態になるのです。
この結果、心拍数の増加や血管の収縮が起こり血圧が上昇します。
[4] 厚生労働省 e-ヘルスネット「一酸化炭素」
2-6.ストレス
ストレスも本態性高血圧の原因になります。
ストレスとは外部から何らかの刺激を受けたときに生じる緊張状態のことを指します。
外部からの刺激には、天候や騒音といった環境的なもの、睡眠不足といった身体的なもの、不安や悩みといった心理的なもの、人間関係や仕事に関連する社会的なものなどがあります。
こうしたストレスを受けると交感神経が優位になるため、血圧上昇を招くのです。
ストレスによって血圧が高くなる状態を「昼間高血圧(ストレス下高血圧)」といいます。
これは診察室血圧が正常で、家庭血圧が高い「仮面高血圧」の一種です。
健康な人であれば、ストレスで一時的に血圧が上昇しても時間がたつと正常に戻るといわれています。
しかし場合によっては血圧が回復しにくかったり、心筋梗塞などの発作につながったりすることがあるため注意が必要です。
2-7.遺伝的要因
高血圧の発症には遺伝的要因も関与するとされています。
実際、家族に高血圧の人がいる場合は高血圧になりやすいとされています。
これは、同居している家族で食事内容が同じであったり生活習慣が似ていたりすることが関連しています。
このような環境的な要因に、遺伝的な要因が合わさった結果高血圧の発症につながる恐れがあるのです。
血縁者に高血圧の人がいても、生活習慣を改めることで高血圧を予防・改善できると考えられるでしょう。
3.本態性高血圧を改善するための生活習慣のポイント
本態性高血圧の発症には生活習慣が大きく関わっています。
この章では、本態性高血圧を改善するために気をつけるべき生活習慣のポイントを解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
ポイント1 減塩を行う
本態性高血圧の最大の原因は、塩分の摂り過ぎとされています。
日本人の食生活は塩分が多くなりやすいため、日頃から減塩へ取り組むことが重要です。
厚生労働省は高血圧の予防・改善のためには、1日当たりの食塩摂取量を6g未満にすることが望ましいとしています[5]。
またWHOのガイドラインでは、成人において1日の塩分摂取量を食塩相当量で5g未満にすることを強く推奨しています[5]。
しかし日本人の20歳以上における食塩相当量の平均値は、男性で10.9g、女性で9.3gで[6]、推奨量を大きく上回っていると分かります。
欧米の研究によると、血圧を下げるには1日当たりの食塩摂取量を6g台前半まで減らさなければならないため[5]、減塩に取り組むことが勧められます。
日頃の食生活では、薄味を意識して塩分を抑えましょう。
しょうゆやソースなどの調味料をかける代わりに、小皿に出してつけるようにするだけで塩分の摂取量を減らせるといわれています。
調味料は、味見しながら必要な分だけ使うようにしてくださいね。
減塩食をおいしく食べるには酢やケチャップ、マヨネーズといった塩分の少ない調味料を上手に使うこともコツの一つです。
ただしケチャップやマヨネーズはそれぞれ糖質や脂質が多めのため、食べ過ぎに注意してくださいね。
また、こしょうやしょうが、柑橘(かんきつ)類といった香辛料・香味野菜・果汁を利用すると、減塩による物足りなさを緩和できると考えられます。
この他、普段から漬物やみそ汁を多く摂る人は食べる量を減らしましょう。
汁物を作る際には、具だくさんにして汁の量を減らすことで塩分量を抑えることができますよ。
調理する際に新鮮な食材を使うと、薄味にしても食材の味を楽しんで満足感を得られるでしょう。
さらに外食や加工食品は多くの塩分を含んでいるため、できるだけ控えることが勧められます。
ラーメンなどを食べる際に汁を飲み干すと、それだけで6g近い塩分を摂ってしまうため注意が必要です[7]。
このように減塩のためには多くのポイントがあるため、できることから始めてみてくださいね。
[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
[6] 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」
[7] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」
ポイント2 カリウムを十分に摂取する

高血圧の予防・改善にはカリウムを摂取するようにしましょう。
カリウムにはナトリウムの排せつを促す作用があるため、血圧を下げる効果が期待できます。
WHOにおいて高血圧予防のために推奨される摂取量は、成人で1日当たり3,510mgです[8]。
しかし20歳以上の日本人のカリウムの平均摂取量は男性で2,439mg、女性で2,273mgのため、推奨量を下回っています[9]。
厚生労働省は実現可能な数値として、成人での1日のカリウムの摂取目標量を男性で3,000mg以上、女性で2,600mg以上に設定しています[8]。
カリウムは野菜類や海藻類、いも類、豆類、果物類などに多く含まれています。
食材中のカリウムは、水にさらしたりゆでたりすると水に溶け出してしまう性質があります。
このため加熱する場合は電子レンジを使用すること、スープなどにして汁ごと食べることなどがおすすめです。
また野菜など生で食べられるものは生のまま食べると、効率良くカリウムを摂取できるでしょう。
カリウムを豊富に含む食べ物や過不足による影響については以下の記事で詳しく解説しています。
[8] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
[9] 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」
ポイント3 食物繊維を十分に摂取する
本態性高血圧の予防・改善には食物繊維を積極的に摂取するようにしましょう。
食物繊維は消化・吸収されずに大腸にまで達する栄養素です。
便の量を増やしたり、腸内の善玉菌を増殖させたりしておなかの調子を整えるはたらきをします。
またナトリウムや脂質、糖質を吸着して体外に排出する作用もあるため、高血圧や肥満などの予防・改善が見込めます。
成人の理想的な食物繊維の摂取量は、1日当たり24g以上です[10]。
しかし20歳以上の日本人における食物繊維摂取量の平均値は、1日当たり男性で19.9g、女性で18.0gです[11]。
厚生労働省は実現可能な数値として、1日当たりの食物繊維の摂取目標量を18〜64歳の男性で21g以上、65歳以上で20g以上に設定しています[10]。
一方女性では18〜64歳で18g以上、65歳以上で17g以上です[10]。
食物繊維は主に植物性食品に含まれており、いも類やきのこ類、海藻類、野菜類、豆類などから摂ることができます。
また主食を玄米や麦ご飯、胚芽米ご飯、全粒粉パンなどに置き換えることで食物繊維を効率良く摂ることができますよ。
食物繊維を多く含む食べ物は以下の記事をご参考にしてください。
食物繊維を含む食べ物は?摂取目標量と摂取量を増やすコツも解説
[10] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
[11] 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」
ポイント4 摂取カロリーを適切に抑える
本態性高血圧の予防・改善には摂取カロリーを適切に抑えることが重要です。
日本では若年から中年の男性を中心に内臓脂肪型肥満を原因とする高血圧が増えています。
こうした高血圧は糖尿病や痛風といった他の病気につながる可能性があるため早めに肥満を解消する必要があります。
肥満とは「BMI」が25以上で体脂肪が蓄積した状態を指します[12]。
肥満は摂取カロリーが消費カロリー(エネルギー消費量)を上回ることによって起こります。
減量のためには摂取カロリーを制限することが大切です。
BMIが肥満に該当する人は「標準体重」を目標体重にして摂取カロリーを抑えましょう。
標準体重はBMIが22.0の状態で、高血圧を含む肥満と関連の強い病気に最もかかりにくい体重です[13]。
標準体重は[身長(m)の2乗]×22で求めることができます[12]。
目標体重が決まったら以下の表を参照し、体重1kg当たりの推定必要カロリーと掛け合わせましょう。
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体活動レベル | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) |
| 18~29歳 | ||||||
| 30~49歳 | ||||||
| 50~64歳 | ||||||
| 65~74歳 | ||||||
| 75歳以上 | ||||||
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成
身体活動レベルについては以下の表を参照しご自身に合ったものを確認してください。
| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |
|---|---|
| 低い(Ⅰ) | 生活の大部分を座って過ごしている場合 |
| 普通(Ⅱ) | 座って過ごすことが多いが、立った状態での作業や徒歩移動、家事、軽いスポーツなどをしている場合 |
| 高い(Ⅲ) | 歩いたり立ったりしている時間が長い場合、あるいは活発な運動習慣がある場合 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成
高血圧や肥満を予防・改善するには、ご自身の体格に合った摂取カロリーに抑えるようにしてくださいね。
[12] 厚生労働省 e-ヘルスネット「肥満と健康」
ポイント5 飲酒量を適切に抑える
本態性高血圧を予防・改善するには、適切な飲酒量に抑えましょう。
飲酒量が多かったり、お酒を習慣的に飲んだりすると高血圧の原因になります。
このため、毎日飲酒する習慣がある人は適切な飲酒量を守り、飲酒しない日を設けることが大切です。
適度な飲酒量は、「純アルコール量」で1日平均約20gです[13]。
主なお酒の純アルコール20g相当の量は以下の図のとおりです。
公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成
ただし適切な飲酒量は体質や性別、年齢によって異なります。
例えば少量の飲酒で顔が赤くなるといった人は、アルコールの分解能力が低いためより少ない飲酒量にとどめましょう。
また女性や高齢者もアルコールの分解能力が低いため、飲酒量を減らしましょう[13]。
この他、お酒を適量に抑えてもおつまみなどを食べ過ぎてしまうと高血圧の要因になりかねません。
飲酒時にはおつまみの食べ過ぎでカロリーや塩分が過剰にならないように注意してくださいね。
[13] 厚生労働省「アルコール」
[14] 厚生労働省 e-ヘルスネット「飲酒量の単位」
ポイント6 有酸素運動を適度に行う
本態性高血圧の予防・改善には、適度な「有酸素運動」も効果的です。
有酸素運動では「血管内皮機能」が改善され、血圧を下げる効果が期待できます。
また運動をすると、たくさんの酸素や栄養を筋肉に届けるために血管が広がり、交感神経の緊張が緩和されることによって血圧が下がります。
ただし、筋トレなどの負荷が高い運動は血圧を急上昇させる恐れがあるため注意が必要です。
高血圧を改善するには、「ややきつい」と感じられる程度の有酸素運動をできれば毎日行うことが勧められます。
しかし仕事などで忙しく、運動時間を設けることが難しい方もいらっしゃるかもしれませんね。
まとまった運動時間が取れない場合には、1回につき10分以上の運動を合計して1日40分以上行いましょう[15]。
またいきなり運動を始めると、体に負担をかける心配があるため注意が必要です。
運動習慣がない人は、生活のなかで活動量を増やすことを意識すると良いでしょう。
例えば、掃除や洗車をする、買い物に行く際には自転車を使うなどがおすすめですよ。
その場合、1週間当たりの総運動時間、あるいは総消費カロリー(総エネルギー消費量)で考えて運動量を調整しましょう。
1回当たりの運動時間を長くして運動回数を減らす、運動強度を下げる代わりに運動回数を増やすなどによりコントロールしてくださいね。
この他、安全に運動を実施するためには準備運動を取り入れることも大切です。
運動前にストレッチや軽い体操などをし、けがの予防に努めてくださいね。
また狭心症などの持病がある場合には、運動の可否や程度を主治医に相談の上、健康状態に合わせて実施してください。
[15] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧症を改善するための運動」
ポイント7 禁煙する
本態性高血圧の予防・改善には禁煙も重要です。
たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素は血圧を上昇させます。
この他にも、喫煙はがんや脳卒中、心筋梗塞、慢性閉塞性肺疾患(COPD)といったさまざまな病気の原因となります。
禁煙するのに遅過ぎることはないため、できるだけ早く取り組むと良いでしょう。
しかし禁煙を難しく感じる方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、たばこをやめたい人向けの専門外来である「禁煙外来」を受診することがおすすめです。
カウンセリングや生活指導といった精神的なサポートの他、ニコチンガムやニコチンパッチを使用した治療を受けることにより、禁煙に期待できます。
一定の基準を満たす場合は、健康保険が適用されますよ。
健康的な毎日を送るために禁煙に取り組んでくださいね。
ポイント8 ストレスをため込まない
本態性高血圧の予防・改善にはストレスを解消することも大切です。
ストレスを感じると交感神経が刺激され血圧の上昇を招いてしまいます。
血圧を安定させるためには日頃から自分に合った方法でストレスを発散しましょう。
ストレス解消には、日頃からリラックスできる時間を設けることがポイントです。
ストレッチをする、好きな音楽を聴く、外の景色を眺めるなどの他、ゆっくりと腹式呼吸をするだけでも効果があります。
また入浴もおすすめです。
入浴では体を回復させたり、リラックスさせたりするときにはたらく「副交感神経」が優位になります。
シャワーだけで済ませずに、ゆっくり湯船につかって心身を労ってくださいね。
ただし就寝直前や熱い温度での入浴は、睡眠を妨げることがあるため注意が必要です。
睡眠には脳や体を休める役割があるため、十分に睡眠を取ることでストレス解消や仕事のパフォーマンス向上などが期待できます。
入浴は就寝の2~3時間前には済ませ、38度のぬるめのお湯で25〜30分程度にすると寝つきが良くなります[16]。
また約40度のお湯で30分ほど汗をかく程度の半身浴でも寝付きの効果が得られるため、自分の体調や好みにあった入浴方法を選択しましょう[16]。
この他、寝る前の飲酒は睡眠の質が低下してしまうため避けるようにしてくださいね。
その他のストレス解消法が知りたいという方は以下の記事をご覧ください。
ストレス発散に効果的な方法は?手軽にスッキリできるおすすめ解消法
[16] 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」
ポイント9 こまめに血圧をチェックする
高血圧の予防のためには毎日の血圧チェックも重要です。
高血圧には自覚症状がほとんどなく、気付けないままに重大な病気を引き起こすリスクがあります。
このため普段から血圧を測定して、自分の血圧を把握しておきましょう。
血圧測定は朝と夜の2回測定し、平均の血圧が分かるよう毎回記録に残しましょう[17]。
正確な血圧を測定するために、朝は起床後1時間以内に、排尿後、食事や内服前の段階で、夜は眠る前に測定しましょう[17]。
測定前はたばこを吸わないこと、飲酒しないこと、カフェインを摂らないことなどにより、血圧を変動させないよう心掛けてくださいね。
また血圧測定は、座って1〜2分間安静にしてから実施してください[17]。
静かで過ごしやすい環境の下、話をしたり体に力を入れたり、動いたりせずに測定しましょう。
測定は座った状態で行い、測定する腕を机に乗せて血圧計の腕に巻く部分(カフ)の高さと心臓の高さが合うような姿勢で行うことがポイントです。
血圧計は手首で測るタイプよりも、上腕にカフ(巻き付ける部分)を付けるタイプの方が正確に測定できるとされていますよ。
家庭用の血圧計は手軽に入手できるため、こまめに測定し高血圧を早期に気付けるようにしてくださいね。
[17] 特定非営利活動法人 日本高血圧学会、特定非営利活動法人 日本高血圧協会、認定特定非営利活動法人 ささえあい医療人権センターCOML「一般向け『高血圧治療ガイドライン2019』解説冊子 高血圧の話」
4.二次性高血圧の原因
二次性高血圧とは血圧上昇を引き起こす病気や薬剤によって高血圧が生じている状態のことです。
原因となる病気には甲状腺や副腎などの病気が挙げられます。
二次性高血圧はこうした原因となる病気を適切に治療することで改善が見込めます。
この章では二次性高血圧の原因となる病気を解説します。
4-1.腎性(腎実質性・腎血管性)
二次性高血圧で最も多いのは腎性高血圧で、「腎実質性高血圧」と「腎血管性高血圧」があります。
腎実質性高血圧とは「慢性糸球体腎症」「糖尿病腎症」「多発性嚢胞(のうほう)腎」などの病気に由来する高血圧です。
このような病気では腎臓の機能が障害され、水分やナトリウムが正常に排せつされないことで高血圧になります。
腎血管性高血圧は、腎臓の動脈(腎動脈)が何らかの原因で狭まり、腎臓から「レニン」という血圧を上げるホルモンが過剰に分泌されることで起こる高血圧です。
4-2.内分泌性
内分泌性高血圧はホルモン分泌の異常によって起こる高血圧です。
原因となる病気の代表例として、脳下垂体の病気である「クッシング病」「末端肥大症」、甲状腺の病気である「バセドウ病」「甲状腺機能低下症」があります。
この他、副甲状腺の病気である「副甲状腺機能亢進症」、副腎の病気である「原発性アルドステロン症」「クッシング症候群」「褐色細胞腫」などもあります。
脳下垂体や甲状腺などは内分泌腺と呼ばれ、血圧や血糖値、代謝などを調整して体の状態を整えるためのホルモンがつくられています。
内分泌腺の病気によりホルモンの分泌に異常が生じることで高血圧が生じるのです。
4-3.血管性
二次性高血圧には血管性の高血圧もあります。
「大動脈炎」や「大動脈縮窄症」といった血管の病気が原因の高血圧です。
大動脈炎とは、心臓から出ている全身で最も太い動脈である大動脈に炎症が起こる病気のことです。
大動脈やそこから枝分かれした血管に炎症が起こることにより、動脈の壁が膨れる動脈瘤が生じる場合もあります。
また大動脈縮窄症は、心臓から出た大動脈が首と腕に枝分かれした部分で狭くなる状態です。
このような病気により、高血圧が生じるのです。
4-4.薬剤誘発性
二次性高血圧には薬剤によって起こる高血圧もあります。
薬剤性高血圧の原因となる薬には、漢方薬や免疫抑制剤、鎮痛消炎剤、経口避妊薬などがあります。
このような薬には、血圧を上昇させる作用を持つものがあります。
これは薬によって体液量が増加したり、血管の太さを調節する血管平滑筋が収縮したり、交感神経が刺激されたりするために起こります。
また血圧を下げる薬の作用を弱めるものもあります。
これにより、一時的または持続的な二次性高血圧を起こすことがあるのです。
5.血圧が高い場合は受診しよう
血圧を測定して高めだったら、速やかに医療機関を受診しましょう。
本態性高血圧治療では、食事や運動といった生活習慣の改善と薬物による治療が基本です。
また二次性高血圧の治療では、原因となる病気の治療が重要です。
このため血圧が高い場合は、特に自覚できる不調がなくとも内科または循環器科を受診し、原因を明らかにすることが重要です。
医師の指示を仰ぎ、個々にあった治療を進めてくださいね。
6.高血圧の原因についてのまとめ
高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態のことをいいます。
高血圧の基準は診察室血圧で、最高血圧140mmHg以上または最低血圧90mmHg以上の場合です[18]。
一方家庭血圧では、最高血圧135mmHg以上または最低血圧85mmHg以上である場合に高血圧と診断されます[18]。
高血圧は本態性高血圧と二次性高血圧に分けられます。
本態性高血圧は食塩の過剰摂取、肥満、飲酒、運動不足、喫煙、ストレスに加え、遺伝的要因などが組み合わさって引き起こされます。
このため本態性高血圧の予防・改善には、食生活を整える、節酒や禁煙に取り組む、有酸素運動を行う、ストレスを解消する、日々のご自分の血圧を把握することが大切です。
一方、二次性高血圧は病気や薬剤が原因の高血圧です。
二次性高血圧で最も多いのは腎性高血圧で、この他にも内分泌性、血管性、薬剤誘発性の高血圧があります。
二次性高血圧を改善するには、原因となる病気の治療が必要です。
血圧が高い場合は、内科または循環器科を受診して原因を明らかにし、適切に治療してください。
自身の生活に高血圧の原因が潜んでいるかを知り、早期の治療につなげる参考にしてくださいね。
[18] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」