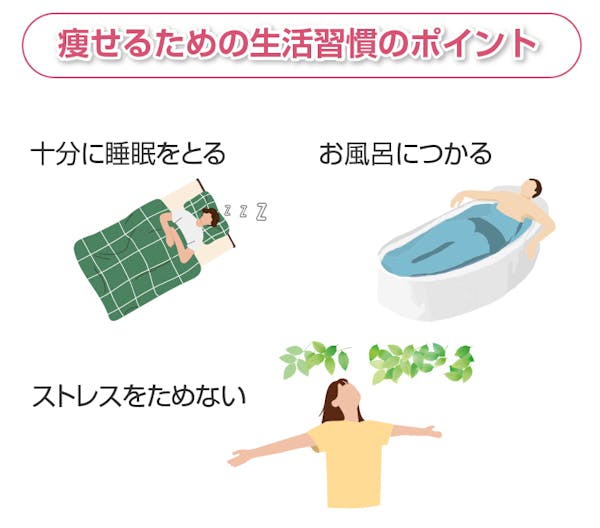痩せるために必要なこととは?食事と運動、生活習慣のポイントを解説
「痩せるにはどうしたら良いんだろう?」
「無理せず簡単に痩せる方法はないのかな……」
無駄な脂肪のないスリムな体、誰もが憧れたことがあるのではないでしょうか。
できれば無理せず引き締まったボディーを手に入れたいという方も多いでしょう。
痩せる方法は実はシンプルで、運動や生活で消費するカロリーを食事で摂取するエネルギーよりも多くすれば良いだけなのです。
そうはいってもダイエットはストレスがたまるため、目標達成まで継続するのは簡単なことではありません。
この記事では痩せるための目標をどのように設定すべきか、また痩せるための運動と食事のポイントを解説します。
さらにダイエットを成功させるための生活習慣も紹介していきます。
目標体重まで痩せるための参考にしてくださいね。
1.痩せるための目標設定方法とは
「どうにか痩せて理想の体型を手に入れたい……」
そんな思いを抱いたことのある方も多いでしょう。
しかし痩せるために大切なのは、本当に痩せる必要があるのか、どの程度痩せるべきなのかをしっかり理解することです。
まずは痩せるための目標をどのように設定すれば良いのかを解説します。
1-1.自分の標準体重を把握する
痩せるためにはまず自分の標準体重を把握することが重要です。
標準体重は糖尿病や高血圧、脂質異常症(高脂血症)などの肥満に関する病気に最もかかりにくい体重とされています。
標準体重は身長(m)×身長(m)×22で求めることができます[1]。
体重がこの標準体重を下回っている方は、肥満や病気の予防といった健康上の理由で痩せる必要はありません。
自分が太っているか、痩せているかを知るには「BMI(Body Mass Index)」という国際的な体格の指標を把握しておくことが重要です。
BMIは体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)という式で求められます[2]。
日本肥満学会はBMI18.5未満を「低体重(やせ)」、18.5以上25未満を「普通体重」、25以上を「肥満」と分類しています[2]。
BMIが肥満と判定された方は、まず普通体重を目指し、最終的には標準体重まで痩せることを目標にすると良いでしょう。
普通体重の方のなかには筋肉を強調したい、スレンダーな体形になりたいなどの理由から今よりも痩せたいという方もいらっしゃるかもしれません。
そうした場合もまずは自分のBMIを知った上で、どの程度痩せるかという目標を定めましょう。
1-2.消費・節制すべきカロリーを把握する
痩せる際の目標体重が定まったら、どの程度のカロリーを運動で消費し、食事を節制すべきかを把握しましょう。
1kgの脂肪を減らすのに必要なカロリーは約7,200kcalとされています[3]。
つまり、脂肪を減らし体重を5kg落とすには、計3万6,000kcalを運動によって消費するか、食事からの摂取を控える必要があるということです。
痩せるためには消費するカロリーを摂取するカロリーよりも多くする必要があります。
そのためどれだけ運動でカロリーを消費しても、それ以上に食事でカロリーを摂取してしまっては絶対に痩せることはできません。
かといって極端に食事を制限してもストレスで長続きせずリバウンドする可能性が高い上に、栄養素の不足により健康を害する危険もあります。
効率的かつ健康的に痩せるためには、運動での消費カロリーの増加と食事での摂取カロリーの減少をバランス良く組み合わせることが重要だといえるでしょう。
[3] 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識 【理論2】肥満・メタボリックシンドロームに対する運動の効果(減量するにあたっての運動の必要性)」
2.痩せるための運動のポイント
「痩せるためにはどんな運動をすれば良いのかな」
効率的に痩せるにはどんな運動が適しているのか、気になりますよね。
脂肪を燃やしてカロリーを消費するには有酸素運動が有効です。
また筋トレを行うと筋肉量が増えてカロリーを消費しやすくなる上に、有酸素運動の効果を高めてくれます。
この章ではそれぞれの運動の効果とポイントを解説します。
ポイント1 有酸素運動を行う
痩せるためにカロリーを消費したい場合は有酸素運動を行いましょう。
有酸素運動は筋肉への負荷が比較的軽いため、長時間続けやすいことが特徴です。
有酸素運動は体内の脂肪を燃焼させることから、体脂肪の減少とそれに伴う体重減少が期待できます。
また有酸素運動はスタミナや粘り強さを意味する心肺持久力も高めます。
有酸素運動で心肺持久力が高まると長く運動できるようになるため、より消費カロリーを増やすことができますね。
なお、通常の運動やスポーツは有酸素運動と無酸素運動が組み合わさっており、運動強度が高くなるに連れて有酸素運動の割合が減少します。
しかし心肺持久力が高まっていると、強度の高い運動でも酸素を利用して脂肪や糖質からエネルギーを使い続けられるようになります。
運動強度が高くなるほど消費カロリーは大きくなるため、同じ時間であれば運動強度の高い運動の方が消費カロリーは大きくなります。
有酸素運動で心肺持久力を高めていけば、より強度の高い運動をより長く行えるようになり消費カロリーを増やせるのです。
ポイント2 筋トレを行う
筋トレは筋力を向上させるための運動ですが、痩せる上でも重要なはたらきがあります。
筋トレを行うと筋肉が増強されて筋力が向上しますが、加えて毎日の生活で消費されるエネルギーである「基礎代謝」が高くなり、消費カロリーが増加します。
筋トレで鍛えられる骨格筋が消費するカロリーは基礎代謝の22%を占めており[5]、基礎代謝に大きく影響するといえます。
このため筋肉が増強されると基礎代謝が高まり、同時に運動する際のカロリー消費量も増加します。
また、筋トレには有酸素運動の脂肪燃焼をサポートするはたらきもあります。
筋トレを行うと成長ホルモンが分泌され、有酸素運動をする際に脂肪が燃焼しやすい状態になります。
成長ホルモンには脂肪細胞の中にある「ホルモン感受性リパーゼ」を活性化し、中性脂肪の分解を促すはたらきがあります。
分解された中性脂肪は有酸素運動のエネルギーとなるため、筋トレによって脂肪が燃えやすい状態になるのです。
このため有酸素運動の前に筋トレを行うことで、より効率的に脂肪を燃やせるようになるといえるでしょう。
一方で筋トレの前に有酸素運動を行ってしまうと、筋トレ後の成長ホルモンの分泌が抑制されてしまうことも分かっています。
脂肪をしっかり燃やすには筋トレから有酸素運動という順番を意識して取り組むことが重要なのですね。
3.痩せるための食事のポイント
「痩せるためにはやっぱり食事も制限しなきゃいけないのかな?」
好きなものを好きなだけ食べながら痩せられたら……と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし痩せるためには摂取カロリーを必ず消費カロリーよりも少なくしなくてはなりません。
しかも、ただカロリー制限をするだけでは必要な栄養素が足りず、健康に悪影響を与える危険があります。
また極端なカロリー制限は大きなストレスとなり、挫折やリバウンドにもつながりかねません。
この章では、痩せるための健康的で長く続けられる食事のポイントを解説していきます。
ポイント1 適切なカロリー制限を行う
痩せるためには適切にカロリー制限を行うとともに、摂取カロリーを消費カロリーよりも少なく抑える必要があります。
そのためにも、自分が日々の生活でどれくらいカロリーを消費しているかを知ることが重要です。
1日の活動に必要とされるカエネルギーは年齢や身体活動の強さによって変わります。
厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、デスクワークがメインでスポーツをしない方を「身体活動レベルI」としています。
また接客などを含む立ち仕事や軽いスポーツを行う方を「身体活動レベルII」、力仕事や活発なスポーツを行う方を「身体活動レベルIII」としています。
それぞれの身体活動レベルの方の1日に必要と推定される体重当たりのエネルギー量は以下のとおりです。
【体重当たりの推定エネルギー必要量】
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体活動レベル | I | II | III | I | II | III |
| 18~29歳 | 35.5kcal | 41.5kcal | 47.4kcal | 33.2kcal | 38.7kcal | 44.2kcal |
| 30~49歳 | 33.7kcal | 39.3kcal | 44.9kcal | 32.9kcal | 38.4kcal | 43.9kcal |
| 50~64歳 | 32.7kcal | 38.2kcal | 43.6kcal | 31.1kcal | 36.2kcal | 41.4kcal |
| 65~74歳 | 31.3kcal | 36.7kcal | 42.1kcal | 30.0kcal | 35.2kcal | 40.4kcal |
| 75歳以上 | 30.1kcal | 35.5kcal | - | 29.0kcal | 34.2kcal | - |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成
身長1.55m、体重50kgで立ち仕事に従事する30代女性が5kg減を目指してダイエットを始めると仮定してみましょう。
この女性は身体活動レベルIIに当たるため、1日当たり必要なエネルギー量は38.4×50=1,920kcalです。
この女性が痩せるには1日の摂取カロリーを1,920kcal未満に抑えれば良いことになります。
一方、目標とする体重45kgの方の1日当たりに必要なエネルギー量は1,728kcalです。
1日当たりの摂取カロリーを1728kcal以下にすれば、目標とする45kgに到達できるのですね。
なお脂肪1kgは約7,000kcalのため、摂取カロリーを1日1728kcalでキープして5kg痩せるには182日間、およそ半年かかることになります。
「もっと1日の摂取カロリーを減らせばより短期間で痩せられるのでは?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし極端なカロリー制限は挫折やリバウンドにつながりやすく、健康に悪影響を与える可能性もあるため無理は避けましょう。
もちろんこれは食事での摂取カロリーに限った話のため、運動で消費カロリーを増やせばより早く達成できますよ。
次にカロリー制限をするに当たり、どんな食べ物を減らせば良いのかをみていきましょう。
ポイント2 脂質と糖質を適切に制限する
カロリー制限の際に減らすべきは脂質と糖質です。
脂質と糖質は、肥満をもたらす体脂肪の大部分を占めている中性脂肪を増やします。
脂質の一種である飽和脂肪酸は摂り過ぎると中性脂肪や悪玉の「LDLコレステロール」を増加させます。
飽和脂肪酸は動物の脂身やバターや生クリームなどの乳製品に多く含まれるほか、パーム油やインスタントラーメンなどの加工食品にも含まれます。
ただし脂質のなかでも、「n-3系多価不飽和脂肪酸」と呼ばれる不飽和脂肪酸には中性脂肪をつくられにくくするはたらきがあります。
中性脂肪を減らせるn-3系多価不飽和脂肪酸はさばやさんま、いわし、ぶりなどの青魚に多く含まれています。
一方糖質を摂り過ぎた場合は、「インスリン」がエネルギーとして使い切れない血液中の糖質を中性脂肪に変えて蓄えてしまいます。
糖質はご飯やパン、麺類などの主食となる穀物やいも類、お菓子や果物などの甘いものに多く含まれています。
特に間食で甘い洋菓子やスナック菓子、清涼飲料水などを摂り過ぎると糖質過多になる危険があるため気を付けてくださいね。
次に、カロリー制限中でもしっかり摂取すべき栄養素について解説します。
ポイント3 たんぱく質を十分に摂取する
痩せたい方はたんぱく質を意識的に摂取しましょう。
たんぱく質は糖質や脂質と並ぶエネルギー産生栄養素の一つであるため、脂質や糖質を制限する場合はその分たんぱく質から必要なエネルギーを得る必要があります。
また、たんぱく質は筋肉や臓器、肌、髪の毛など体の組織を構成する細胞をつくり、生命維持に欠かせないホルモンや酵素の材料にもなります。
筋肉を鍛えて量が増えると基礎代謝が上がるため、たんぱく質を十分に摂取することは日々のカロリー消費量を高い水準で維持することにつながります。
たんぱく質の成分のなかでも、筋肉をつくるのに重要なのが「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」です。
分岐鎖アミノ酸はまぐろの赤身、鶏肉、かつお、牛肉、卵、牛乳などに特に多く含まれています。
なお、たんぱく質を含む食品の中には飽和脂肪酸を多く含む肉類や乳製品もあります。
痩せたい方は赤身肉を選ぶ、脂身や皮を取り除く、低脂肪乳を選ぶといった工夫すると良いでしょう。
ポイント4 食物繊維を十分に摂取する
痩せるためには食物繊維を意識的に摂取しましょう。
食物繊維は食べ物のなかで、ヒトの消化酵素で分解できない成分の総称です。
食物繊維には脂質や糖質、塩分などを吸着して体外に排出するはたらきがあります。
食物繊維を多く摂ることで、食品中の脂質や糖質の吸収を抑えることができるのですね。
また食物繊維を含む野菜や豆類、きのこ類、海藻類などは腹持ちが良く、カロリーが低めな食品が多いことが特徴です。
ポイント5 栄養バランスに留意する
痩せるためには摂取カロリーを減らすだけでなく、栄養バランスに留意してください。
カロリー制限の際は食べる量を減らすことにばかり考え、必要な栄養素まで気が回らなくなる事があります。
必要な栄養素が欠乏すると、例えば食物繊維不足による便秘やカルシウム不足による骨粗しょう症、鉄分不足による貧血、月経異常などに陥る危険があります。
健康のためには炭水化物、たんぱく質、脂質のエネルギー産生栄養素をバランスよく摂取する必要があります。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、エネルギー産生栄養素の目標とすべき摂取バランスは以下のように設定されています。
【エネルギー産生栄養素バランス】
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物(糖質) | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物(糖質) |
| 18~29歳 | 13~20% | 20~30% | 50~65% | 13~20% | 20~30% | 50~65% |
| 30~49歳 | 13~20% | 20~30% | 50~65% | 13~20% | 20~30% | 50~65% |
| 50~64歳 | 14~20% | 20~30% | 50~65% | 14~20% | 20~30% | 50~65% |
| 65~74歳 | 15~20% | 20~30% | 50~65% | 15~20% | 20~30% | 50~65% |
| 75歳以上 | 15~20% | 20~30% | 50~65% | 15~20% | 20~30% | 50~65% |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成
このバランスを参考に栄養素を摂取するよう心掛けると共に、脂質や糖質を制限する場合も極端な制限は絶対にやめましょう。
また、エネルギー産生栄養素以外にもビタミン、ミネラルは体に欠かすことができない栄養素のため、しっかり摂取してください。
厚生労働省は栄養バランスの観点から主食、主菜、副菜を組み合わせた「健康な食事」を推奨しています。
【健康な食事】
- 主食……ごはん、パン、麺類などで、炭水化物を多く含む
- 主菜……魚や肉、卵、大豆製品などを使った料理で、たんぱく質や脂質を多く含む
- 副菜……野菜などを使った料理で、ビタミンやミネラル、食物繊維などを多く含む
日々の献立を考える際に参考にしてみてくださいね。
ポイント6 ゆっくりよく噛んで食べる
痩せるためにはゆっくりよく噛んで食べる習慣を付けましょう。
ヒトの脳が食事を始めてから満腹を感じるまでは、20分程度かかるといわれています[6]。
早く食べる習慣のある方は、満腹を感じる前に食べ過ぎてしまう可能性が高いのです。
時間をかけてよく噛むことで、食事の量が少なくても脳の満腹中枢が刺激されます。
このため食べ過ぎになりにくく、肥満を予防できます。
まずは一口当たり30回噛んで食べることを意識してみましょう[7]。
どうしても早く食べてしまうという方は、食材を大きめに切る、硬めにゆでるなどの工夫をしてみましょう。
また根菜や海藻などの食物繊維の多いものや硬いもの、こんにゃく、たこのような弾力のあるものなど、歯応えのある食材を選ぶこともポイントです。
ポイント7 アルコールを控える
痩せたい方はアルコールを控えましょう。
まずアルコール自体が1g当たり7kcalと高カロリーな飲み物です[8]。
ビールやワインなどには糖質やたんぱく質が含まれているため、それらのカロリーも合わせて摂取することになります。
梅酒などの砂糖を用いたお酒やカクテルなどの甘い清涼飲料水で割ったお酒の場合は、さらにそれらのカロリーまで追加されるため注意が必要です。
加えてアルコールには食欲を増進する作用もあります。
揚げ物などのおつまみを食べながら飲んだり、締めにラーメンを食べたりして後悔した経験のある方も多いでしょう。
アルコールはエネルギーとして使われやすく、他の脂質や糖質よりも先に分解されます。
そのため使われずに余った脂質や糖質が中性脂肪となって蓄積されてしまうのです。
これとは別にアルコールは摂取し過ぎると、肝臓で分解される際に中性脂肪の合成が促進されます。
アルコールには中性脂肪を直接的にも間接的にも増やす性質があるといえるでしょう。
そのため、痩せたい方はまずお酒の量を控えましょう。
厚生労働省は「節度ある適度な飲酒」として1日当たり純アルコールで20g程度までに抑えることを推奨しています[9]。
代表的なお酒の量に換算すると以下のとおりです。
公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成
またおつまみは枝豆や海藻サラダ、豆腐、鶏ささみなど、極力低カロリーで食物繊維やたんぱく質の多いものを選びましょう。
禁酒しない場合はこの章の内容を参考に、上手にお酒と付き合ってみてくださいね。
[9] 厚生労働省「アルコール」
ポイント8 水分を十分に摂取する
痩せるためには十分な水分摂取も欠かせません。
水分をしっかり摂取すると血行が良くなり、全身に栄養素が行き渡って基礎代謝が高まるため、消費カロリーがアップします。
また食前に水を飲むようにするとお腹が満たされるため、食欲の抑制にもなります。
ただし短時間に多くの水を飲み過ぎると体内のミネラル濃度が下がり「水中毒」と呼ばれる症状を引き起こす恐れがあるため、水は一度に大量に飲むのではなく、こまめに補給するようにしてくださいね。
4.痩せるための生活習慣のポイント
「運動や食事以外にも、痩せるためにできることはあるのかな?」
痩せるには消費カロリーを増やし、摂取カロリーを減らすことが基本ですが、それ以外にも気を付けたいことがあります。
この章では日々の生活のなかで手軽に実践できる痩せるためのポイントを紹介します。
ポイント1 十分に睡眠をとる
痩せるためには十分な睡眠時間を確保しましょう。
眠っている間には「成長ホルモン」が分泌されます。
成長ホルモンには筋肉を発達させると共に、脂肪細胞の中にある「ホルモン感受性リパーゼ」を活性化させて中性脂肪の分解を促すはたらきもあります。
また眠っている間には「レプチン」という食欲を抑えるはたらきのあるホルモンも分泌されます。
しっかり睡眠をとっているとレプチンが十分に分泌されますが、睡眠不足になると「グレリン」という食欲を増進させるホルモンが分泌されてしまうのです。
十分な睡眠時間をキープすることで、食欲が抑えられて食べ過ぎを防げるのですね。
ポイント2 お風呂につかる
痩せるためには温かいお風呂につかるようにしましょう。
食事や運動に気を付けていても痩せにくい方は体温が低い可能性があります。
体温が低いと、それだけ基礎代謝が下がってしまうのです。
入浴には体温を上げる効果があります。
シャワーだけで済まさず、ぬるめのお湯にじっくりつかって体の芯まで温まる習慣を付けましょう。
お湯で体温が上がるだけでなく、全身に水圧がかかることでも血行が良くなって基礎代謝アップにつながります。
ポイント3 ストレスをためない
痩せるためにはストレスをできるだけためないようにしましょう。
慢性的にストレスを感じ続けると、ストレスホルモンとして知られる「コルチゾール」が過剰に分泌されてしまいます。
コルチゾールは適量であれば脂質や糖質の代謝を行うため痩せるのに適していますが、過剰になると問題が生じます。
コルチゾールは過剰に分泌されると成長ホルモンのはたらきを阻害し、基礎代謝を低下させて痩せにくい体にしてしまいます。
またコルチゾールが過剰になった場合は、インスリンが大量に分泌されて余剰エネルギーを中性脂肪として蓄えるはたらきが強くなってしまいます。
加えてコルチゾールには食欲を増進させるはたらきがある上に、食欲を抑えるレプチンを抑制してしまうのです。
ストレスでやけ食いをしてしまう原因の一つはコルチゾールが過剰に分泌されているからなのですね。
現代社会ではストレスを感じないことはほぼ不可能なため、できる限りためこまずに解消していくようにしましょう。
5.痩せる方法についてのまとめ
痩せるための方法は極めてシンプルで、運動や生活で消費するカロリーを食事で摂取するエネルギーよりも多くすることです。
痩せるためには、まず自分の適正体重とBMIを知り、目標体重に到達するのにどの程度のカロリーを運動で消費し、食事で節制すべきかを把握しましょう。
痩せるための運動としてはウォーキングやジョギングなどの有酸素運動が有効です。
また筋トレも基礎代謝を高め、有酸素運動の効果を高めてくれるため、併せて行うようにしましょう。
痩せるためには食事で摂取する脂質や糖質を控え、カロリーを適切に制限する必要があります。
一方で筋肉を維持するためのたんぱく質や脂質、糖質の吸収を抑える食物繊維、生命維持に必要なビタミン、ミネラルなどの栄養素はバランス良く摂取しましょう。
お酒を控える、よく噛んで食べる、水分をしっかり補給するのもポイントです。
日々の生活では、十分に睡眠をとる、入浴習慣を付ける、ストレスをためないことを心掛けてくださいね。